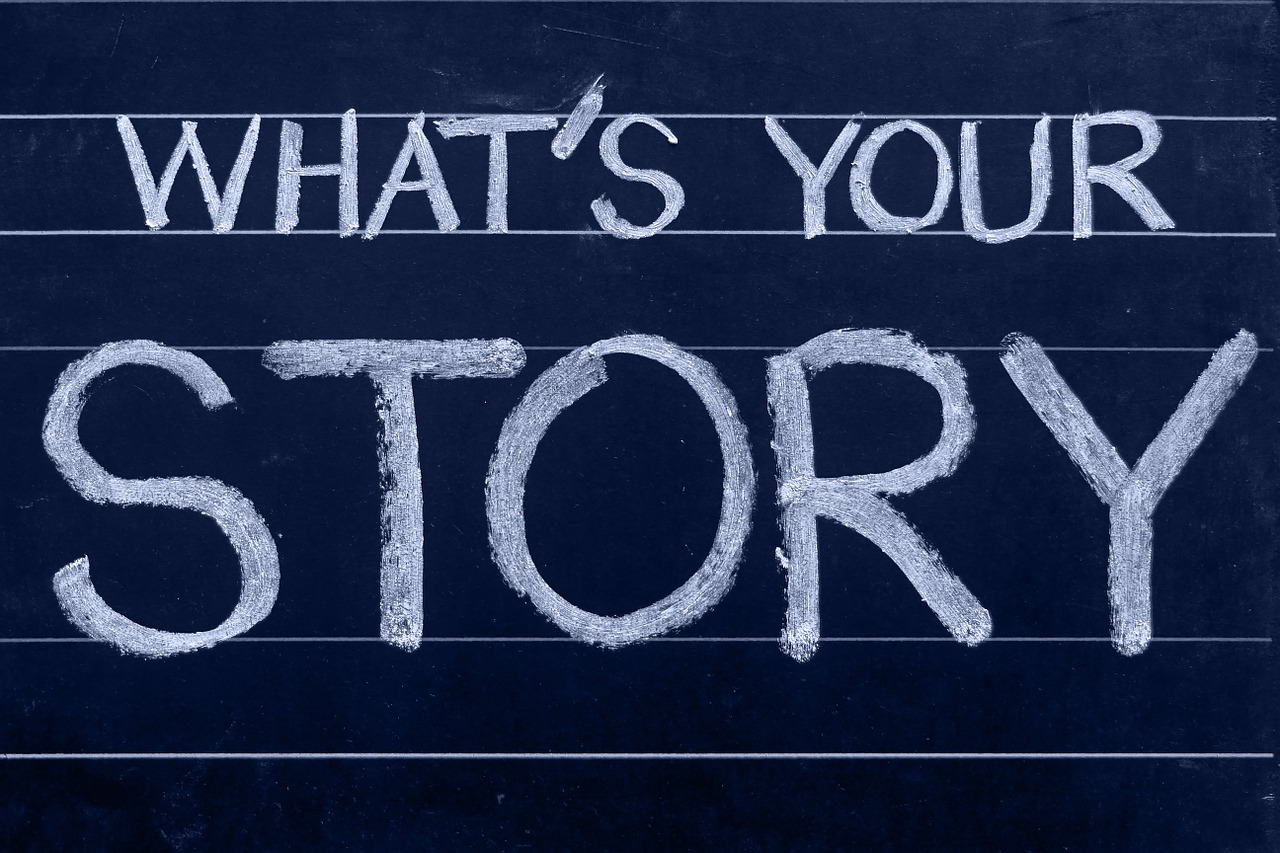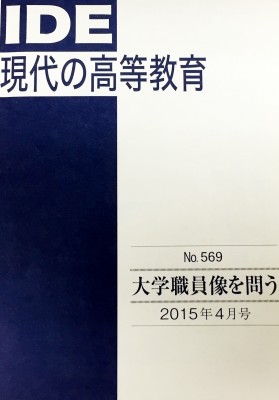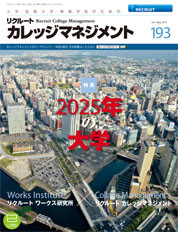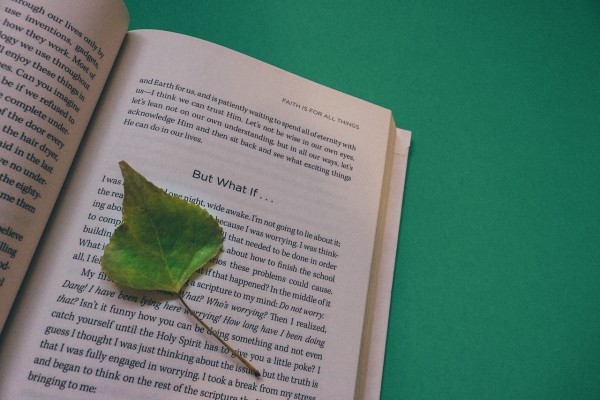『未来形の大学』市川昭午著(玉川大学出版部)は名著である。
現在大学人が直面している問題について、数多くの示唆を与えてくれる。
読書ノートをご紹介しよう。
今回からⅡ章に入る。
このページの目次
Ⅱ章 一般教育―知識階級の消滅と教養教育の衰亡
1.戦後大学教育の最大混乱要因
一般教養・一般教育・教養教育
- 「大学における一般教育は、戦後のわが国の教育改革において理念的にも、また、実際的にも、恐らく最も重要でかつ困難な問題を含むもの」。
- 一般教育は普通教育と教養教育からなる。
- ヨーロッパでは普通教育は中等教育段階で完了するものとされ、大学教育には含まれていない。
- わが国もまた旧学制時代はそれに倣ってきたが、第二次大戦後の新学制では大学でも行われることになった。
- それは米国教育使節団の指導があったのと新制高校の教育課程では旧制高校の教育課程を包摂することが困難になったため。
- 一般教育は新制大学の大きな特色となった反面、旧制大学とは異質なものだった。
- 数多くの改善施策と各大学における努力にもかかわらず、ついに定着するには至らなかった。
- 一般教育に関しての二つの疑問。
- 一点目。なぜ二度にわたって改称したのか。
- 新制大学発足当初は「一般教養」と称したが、まもなく「一般教育」となり、最近は「教養教育」あるいは「共通教育」と呼ばれるようになった。
- 1950年の改定では「一般教養科目」の名称が「一般教育科目」に変更された。
- 両者の主な違いは、前者が外国語を含むのに対して、後者が含まない点。
- 新しい学制が動き出してみると、教養教育の理念を謳っているだけでは済まず、高等普通教育をどうするかという問題に取り組まなければならなくなったため、一般教養より実態に近い「一般教育」の方が適切と判断されるようになったからではないか。
- 一般教育から「教養教育」への名称変更はごく最近のこと。
- 1991年の改正で、大学設置基準から一般教育の名称が消えてしまった。
- この変更は一般教育を構成していた基礎教育的部分が切り離され、一般教育が教養教育に純化される可能性が出てきたことに伴うもの。
理念は教養教育、実態は普通教育
- 二点目の疑問。新制大学ではなぜ普通教育でなく一般教育と呼ばれてきたのか。
- 一般教育等の実態は、教養教育というよりはむしろ専門教育の基礎教育・準備教育が中心であり、教育条件が劣化したことを除けば、旧制高等学校の高等普通教育と大きくは変わらなかった。
教養教育の三方式
- 専門教育に対する基礎教育・準備教育であれば、その内容はおのずから決まってくるが、教養教育がどうすれば可能になるかはきわめて難しい問題。
- アシュビーの三つの方式
①カリキュラム編成を工夫することによって、すべての学生が習得すべき文化の共通核を伝えようとするもの。
②専攻分野の学習に打ち込むことによって、教養を身につけさせようというもの。
③寄宿制カレッジにおいて教員と学生が生活をともにし、知性を磨きあうことが教養を身につける最も効果的な方法であるとするもの。
- 戦後のわが国における一般教育問題論議は、アメリカの影響を強く受けたためか、カリキュラムをどう構成するかという問題に終始した嫌いがある。
- しかし、高等普通教育であればともかく、教養教育はカリキュラムを工夫すればどうにかなるというものではない。
- リベラル・エデュケーションの伝統の下では、本来生活と学問が結びついていたことが忘れられてはならない。
- リベラル・エデュケーションの目的である全体性や統一性を得るためには生活のあらゆる面に着目することが求められるのであり、カリキュラムはその一面にすぎない。
- したがって、教養教育に関しては、カリキュラムだけでなく、その制度的特質に注目する必要がある。
- それは、教員一人当たり学生数が少ないこと、親密な学生仲間による人間形成の環境が整っていること、学力あるいは社会的に選ばれた集団であること、それに由来する特権的な雰囲気とノブレス・オブリージュの空気といったもの。
- 大衆化された高等教育にこうした教育条件を期待することは難しい。
- ドイツ近代大学の理念である「学問研究を通じた自己形成」などは、それ以上に無理。
![未来形の大学 [高等教育シリーズ] (高等教育シリーズ) 未来形の大学 [高等教育シリーズ] (高等教育シリーズ)](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41A4BV9A8YL.jpg)
posted with ヨメレバ
- 作者:市川 昭午
- 出版社:玉川大学出版部
- 発売日: 2001-04-20
The following two tabs change content below.

大学職員ブロガーです。テーマは「大学職員のインプットとアウトプット」です。【経歴】 大学卒業後、関西にある私立大学へ奉職し、41年間勤めました。 退職後も、大学職員の自己啓発や勉強のお手伝いをし、未来に希望のもてる大学職員を増やすことができればいいなと考えています。【趣味】読書・音楽(主にジャズとクラシック)・旅 【信条】 健康第一であと10年!
最新記事 by 瀬田 博 (全て見る)
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(3) - 2018年12月25日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(2) - 2018年12月20日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(1) - 2018年12月19日