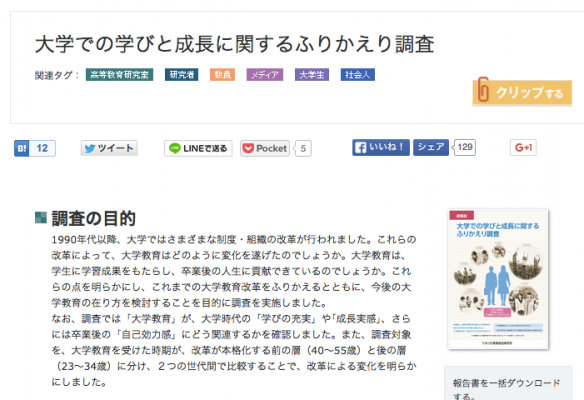このページの目次
はじめに
大学行政管理学会の特別シンポジウム(第3回近畿地区研究会)に参加してきた。
テーマは「2040年代における大学の役割と使命ーそのために今、為すべきことー」。
今回は、第3部 事例紹介と第4部 質疑応答である。
筆者が重要だと感じたことをご紹介する。
■と き:2018年12月9日(日)13:00-17:35
■ところ:龍谷大学深草キャンパス
【第1部】2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(1)
【第2部】2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(2)
【第3部】2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(3)
▼当日の概要についてはこちら。
第3部 事例紹介

関西学院大学将来構想「Kwansei Grand Challenge2039」/小野 宏氏(総合企画部)
- 中期総合経営計画全体を「内部質保証」としている。
- 各部門のサイロ化(タコツボ化)のために、部署がバラバラ。それをどう統合して同じ方向を向かせるか。それを防ぐのが長期戦略とKGI・KPI指標。
- IRより、マネジメントと指標がしっかりとしていないといけない。
■Kwansei Grand Challenge2039&中期総合経営計画
J-Vision22の策定と浸透 学校法人常翔学園 中長期目標・計画〜創立100周年に向けて〜/松浦 靖氏(経営企画室)
- 策定に当たっては、具体的な数値目標(中期目標)を掲げて戦略的に取り組んでいくことを、理事会・評議会で決議。
- のち第Ⅱ期では、定性目標も取り入れた。
- 教職員情報共有サイトによる情報共有を行っている。「数字で見る学園」では、「学生・生徒募集」「教育・研究」「就職・進学」に関連するデータを数値目標の参考になるように掲載している。
- IRは、学長等による意思決定に資する情報を提供することを目的としている。
- 複線型の人事制度(総合職と専任職)
- 管理職は年俸制度(基本年俸+業績年俸+役職年俸)
中長期計画の実効性を高めるための工夫ー龍谷大学における試みー/岡田雄介氏(学長室)
- 中長期計画の成否を左右する組織文化。
- 課題はトップダウン、ボトムアップの両面を兼ね備え、機会ロスを生まず、組織構成員の参画意欲を維持し、責任の所在を明確にしながら、大胆な改革を実施できるか。
- 「将来構想タスクフォース」を設置。特徴は、教職協働型で編成し、各学部・事務から次世代の人材を選出していることであり、目的は、人材開発(育成)と帰属意識の発揚。
- グローバル化対応のために、毎年全体の2%外国人教員を採用すれば、20年で40%になる。
吉武博通氏のコメント
- 組織づくりと人事は、精緻な仕組みが必要。
- 計画策定が年中行事になると「中期計画病」になる。それを防ぐには、計画策定を対話のツールにすること。
- トップと学部長が話し合う「トップミーティング」の必要性。
- 計画を柔軟に見直すのは良いこと。
- IRは、何を出したいのかを明確に。
- 大学に機会損失はない。ちゃんと前に進むようにじっくりとやることが大事。
- 30%の教員の同意が得られると、大学は変わる。
- 多くの企業が人材育成に失敗している。シニア・マネージャー以上の仕事は人材育成。それをこれまでやってこなかった。
- 現場に足を運び、話し合う。人材育成はコミュニケーション。
第4部 質疑応答
Q:公財政支出に関連して、大学が行うべきことは。
A:教育の質の保証だが、学生の学修時間の獲得が大事で、これですべての問題が解決する。
Q:正課外教育の評価方法について。
A:本学には「ダブルチャレンジ制度」がある。これまで外国での正課外教育が単位化できなかった。単位化が必要か?間接評価か直接評価かという問題がある。
Q:ゴールについて、中長期計画と超長期計画との関係について。
A:内部質保証についていうと、指標が回っているかというような自立性のほうが重要。
Q:責任は権限とセットで、それを一致させて運営すべきだが、目標達成のためのマネジメントとは。
A:
・評価制度は人事と連動しない。人事考課はきっちりとやる。
・教員はむずかしい。
・理事会のような最上位の責任をどう評価するのか。
・パフォーマンスは評価されるべき。これはガバナンスにかかわる本質的な問題。
Q:来年職員になる。若手人材への考えは。
A:社会人になっても学び続けること。知は力なり。努力すること。
最後に村田 治氏から
- 大学は教員中心に意思決定されているが、そこに職員を入れたい。
- 教職協働というが、職員はあくまで支援だった。今後それはなくなる。教員の一部と職員がやる。
- 意思決定こそ職員がやる。そのために勉強する必要がある。
- 地方大学はこれから、機能分化から多様性が必要とされる。とくに私立大学において顕著。
感想
中長期計画のない組織は、羅針盤のない船と同じである。
どんなに優秀な人間がいて、立派なハードウェアがあっても、向かうべき目的地と計画が共有されていなければ、それらのリソースが有効に使われることはない。
「計画を立てたのはいいが、修正ばかりやっているから意味がない」という理由で、計画策定に否定的な大学があると聞く。
吉武氏が述べておられるように、その時点の状況によって計画は柔軟に見直すべきであるし、そのことが教職員の対話につながる。
そういった教職員のコミュニケーションこそが、もっとも重要だと考える。
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(3) - 2018年12月25日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(2) - 2018年12月20日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(1) - 2018年12月19日