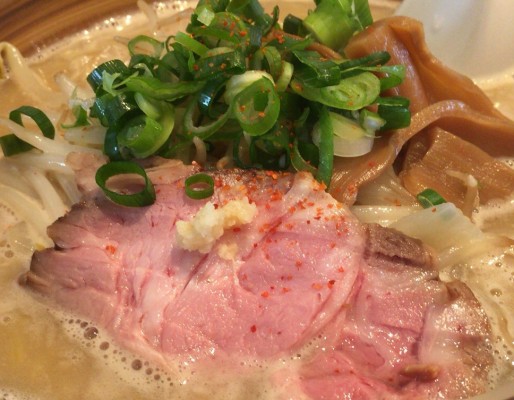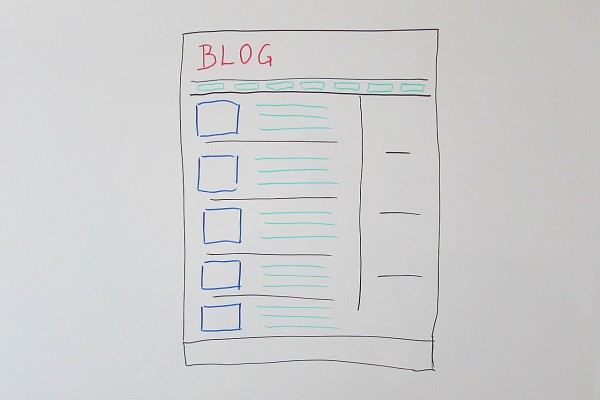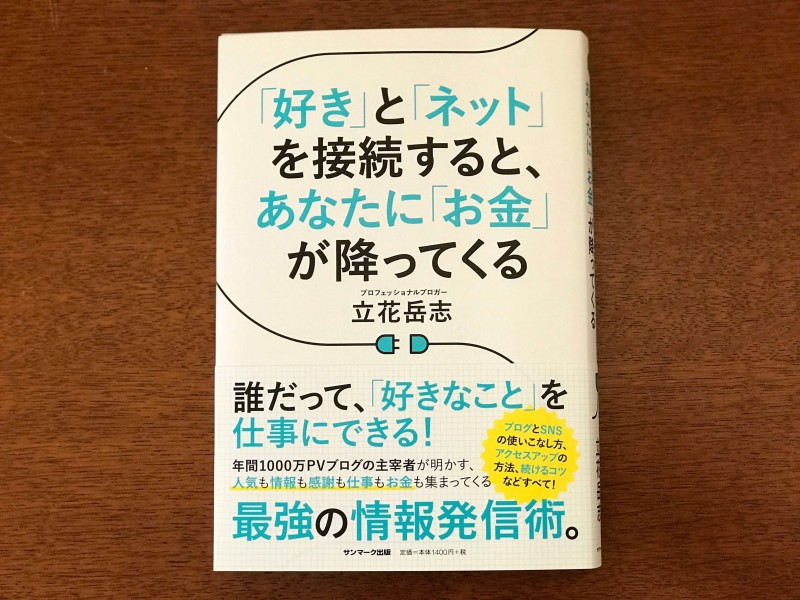このページの目次
トーク・アラウンド・ブックス2015@奈良県立図書情報館
■2016年2月12日(金)18:00〜19:50
■奈良県立図書情報館
■参加者:20名(女性15名)
第6回。今回が最終回です。
テキストはミランダ・ジュライの『いちばんここに似合う人』。
今回のケーキ&コーヒー
毎回実費でいただく本日のケーキ&コーヒー。
▼ケーキ(ココナッツ、チョコレート、キャラメル)。京都のKathy’s Kitchen製です。

▼コーヒー(誠光社のランベルマイユ・ブレンド。コクはあるけどすっきりしたあと味)

それでは、ご紹介しましょう。
堀部篤史氏のトーク 答えや解決策があるのが文学ではない。安易な答えを出さないからすばらしい。
これまでの作家たちとの違い
- 同時代の作家であり、
- リアルタイムで新作を読むことができる
- 専業小説家ではなくアートや音楽の分野から世に出る
- 作品を書く前にインターネットが存在していた世代
岸本佐知子氏の翻訳作品
- 『偏愛小説集』というアンソロジー
- 『作家断片集』(ハヤカワ)
いま注目すべき翻訳者
- 藤井 光氏
柴田元幸氏も推薦、認めている“現代”の翻訳者。
ミランダ・ジュライの活動
- “Right Growl”ムーブメントー『私はドアにキスをする』、パンクやロックの男性性に反発、ライブ会場やZineをメディアとしたインディペンデントな発信をしたバンド。
- Sleater Kinneyのミュージック・ビデオをジュライが制作
- コミュニケーションアプリ“Somebody”→アサインメント
- インスタレーション“The Hallway”→鑑賞者とのコミュニケーション
- オノ・ヨーコ『グレープフルーツジュース』。読者にアサインメントを与える言葉→「グレープフルーツ・オノ・ヨーコ」というTwitterアカウント
- ソフィ・カルー現代美術作家。“Double Game”という作品は、ポール・オースターの『リヴァイアサン』登場人物のマリアをソフィ自身が模倣している。
ミランダ・ジュライ その作品の特徴
- チャイルディッシュな「決め事」や自身の意志を超えた部分による「偶発性」→自我や自分自身からの逃避
- 自意識の重さとコミュニケーションの困難さについて、多角的にいろんなアプローチ
- 人と関わることの困難さ→人と関係する際に生じる違和感やすれ違い
そして、堀部氏はこう述べておられます。
自意識からくるコミュニケーションに苦しんでいる人たちに、こういう小説は救いになる。
全部理解できることが書いてある小説作品は✕。
答えや解決策があるのが文学ではない。安易な答えを出さないからすばらしい。
検索で得た知識は、それ以上のものにならない。おなじところをグルグル廻っているだけ。ふだん求めないものを見たり読んだりすることが大事。
まとめ
第4回から参加したこのイベントですが、毎回たっぷりと楽しませていただきました。
そして毎回たくさんの「リンク」によって、知らない作家などを知ることができ、勉強にもなりました。
自分の好きな書物や音楽を気ままに楽しむのもいいのですが、ときには「ふだん求めないものを見たり読んだりすることが大事」だと強く感じました。
なぜなら、知らないことは山ほどあるのですから。まだ知らない(けれど自分が好きになるかもしれない)世界を探す旅に、ときには出る必要があります。
そんなワクワクするようなきっかけを与えてくださった「トーク・アラウンド・ブックス」に感謝します。
次年度のイベントは?
- 次回はグループ形式で、自分のすきな本を紹介するやり方を考えている。
- 『私自身の見えない徴』エイミー・ベンダーという小説。
とのことでした。
楽しみです。
関連図書リスト
「トーク・アラウンド・ブックス2015 第6回」関連図書リスト
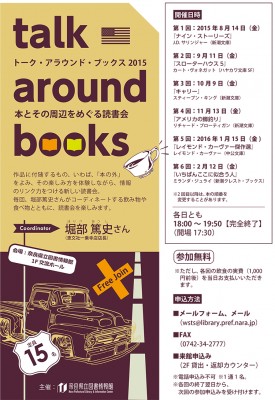
これまでの「トーク・アラウンド・ブックス」の記事はこちら!
■第5回

■第4回
トーク・アラウンド・ブックス2015@奈良県立図書情報館で『アメリカの鱒釣り』についてトークする
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(3) - 2018年12月25日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(2) - 2018年12月20日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(1) - 2018年12月19日