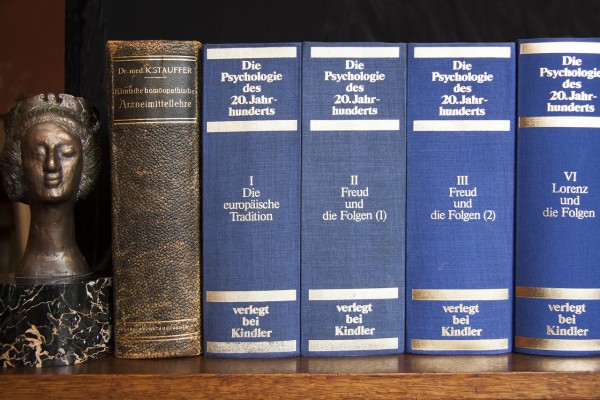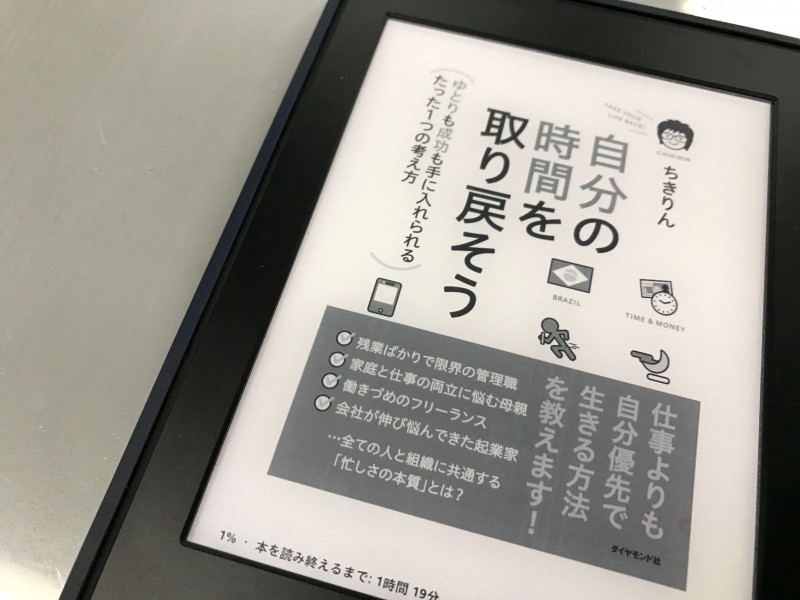『戦略的大学職員養成ハンドブック』岩田雅明著(ぎょうせい)の第6章には「大学職員のキャリア紹介―5人の職員たちの、これまでと今、そしてこれから」が収められている。
第一線で活躍されている(こられた)方々の、設問に答える形式の内容になっている。
大学職員の皆さまにぜひ読んでいただきたいと思い、取り上げたしだいである。
本章のはじめに著者の岩田氏は、以下のように述べている。
大学職員は、言われたことをつつがなく処理していくというような、これまで許されたような働き方が許されなくなってきている。
自分たちの力で大学を変えていくという強い思いを持ち、自分の果たすべき役割をきちんと果たすだけでなく、周囲をも巻き込んで、大学改革を推進していくという覚悟が求められている。
そのための参考となる取り組み、思いといったものも、それぞれの方たちのキャリアの足跡の中には、数多く散りばめられている。それらも、ぜひ皆さんの、これからの働き方の参考としていただければ幸いである。
本書については、あらためて全体をご紹介したいと思っているが、今回からはこの5人の記事をご紹介する。
第1回目は、岩井絹江氏(学校法人渡辺学園 常務理事、理事長補佐業務 東京家政大学学長補佐、進路アドバイザー)である。
筆者が重要だと感じたことを、以下ご紹介しよう。
出会いと現場感覚を大切に
ネットワークを築くための出会い
- 外部の研修会の効用は、幅広いネットワークを築くための出会い、情報交換の場があるということ。
- ネットワークを利用して、学生を育成するに際しての基本的な指針といったことや、学生への対応力を身に付けるうえで、多くの気づきを得ることができた。
- (他大学の)優れた事例、取り組みをしっかりと吸収し、それを自分の大学に当てはめて調整し、改善に生かしていく。
- 「これからの大学職員は学外に目を向ける必要がある」という考え方の上司だった。
- 大学業界以外の異業種の方たちとの交流も、貴重な体験だった。
- 大学業界にいると、あまり社会を意識しないでも過ぎてしまうことも多いが、若い時に「時代を読む柔軟な思考と実行力の必要性」を学ぶことができた。このことが、現在の大学の経営に従事するという仕事に大変役立っている。
大学職員へのメッセージ
- 大学全体をプラス思考で見渡すことで自分の学園、大学の良さを理解し、教育を支える潤滑油であり牽引役でもある大学職員の仕事に自信と誇りを持って努力していってほしい。
まとめ
ともすれば職場に閉じこもりがちな大学職員。
入試、キャリアといった比較的外部と接触することの多い部署であっても、その実態は限られた人脈との付き合いであるかもしれない。
岩井氏のように、若い頃から積極的に外部の研修会に参加することは、情報収集とネットワーク構築のために必須のことだろう。
さらに管理職になってからの異業種の人たちとの交流も、経営を考える意味でも有用なことであるに違いない。
同氏は、現在も進学相談会、高校での説明会や進路講演、高校訪問を続けているそうだ。そういった「現場感覚」もまた、経営に活かされているのであろう。
【目次】大学職員のキャリア

- 作者:岩田 雅明
- 出版社:ぎょうせい
- 発売日: 2016-02-26
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(3) - 2018年12月25日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(2) - 2018年12月20日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(1) - 2018年12月19日