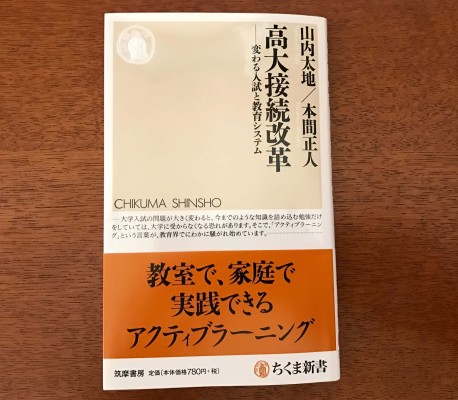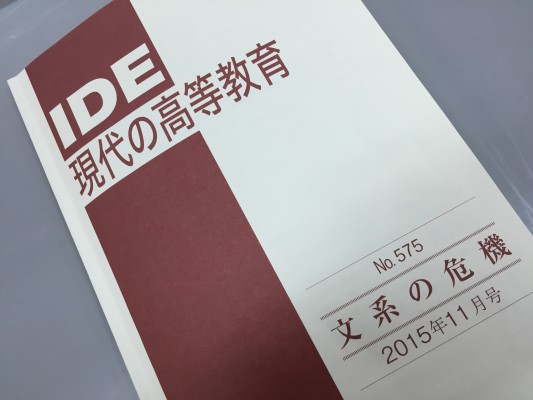『シャープ崩壊』日本経済新聞社編(日本経済新聞出版社)
内容紹介にこうある。
これは人災だ。
シャープは権力者の人事抗争の末に悲劇が起きた。堺工場に代表される液晶事業への身の丈にあわない巨額投資の失敗はもちろんだが、経営危機に陥った後に内紛が激化し、効果的な打開策を打ち出せず、傷口が広がったのだ。名門企業が権力抗争によって瞬く間に転落する姿を描く。

- 作者:日本経済新聞社
- 出版社:日本経済新聞出版社
- 発売日: 2016-02-18
ベストセラーだそうだが、筆者の住む大阪では、地元柄か発売後から平台に置いている書店が多かった。
ともすれば財界の御用聞きと揶揄される日本経済新聞だが、三井不動産レジデンシャルが横浜市都筑区池部町で販売した杭打ち偽装マンション事件でも気骨のある報道を行っているようだ。
そして、本書も綿密な取材にもとづく、読みやすく、わかりやすい内容の良書となっている。
いまやベストセラーだが、筆者の住む大阪では、地元柄か発売後から平台に置いている書店が多かった。
凋落の原因は、本書でも繰り返し指摘されているように、
- 特定事業(液晶、太陽電池)への過剰な投資
- 経営陣の権力抗争
- 垂直統合生産方式への固執
などのようだ。
いまも復活をめざして、現場で奮闘している社員のことを思うと胸が痛む。
反面、現高橋社長に引導を渡されるまで、「個室、専用車、専属秘書」付きで本社にいた元会長、社長たち。
成功体験を忘れられず、いつまでも権力にすがりつく前経営陣には嫌悪感を感じる。
ユニクロの場合
「柳井氏『市場はシビア』、失敗認め、戦略を転換、ユニクロ値上げ『評価されず』」
2016日4月13日付日本経済新聞(朝刊)の記事である。
柳井氏は値上げを戦略ミスと認め、即座に値下げを実施している。
そして、事業拡大とともに大企業病に陥っていることへの危機感もあらわにしているとの報道である。
後者については「組織を大きく変える」ために、社内組織を5〜6人程度の小さなチームを多数つくり、プロジェクトごとに経費管理から人材育成まで責任を負う組織へと改め、重視する「経営者感覚」を社員が持てる環境を整える、という。
ユニクロ(ファストリテイリング)といえども危機は来るだろう。
だが、このような対応をトップがとり続けるかぎり、社員もステークホルダーも納得こそすれ、絶望することはないように思われるのである。
まとめ
本書で述べられている内容は、どの組織も他人事ではないと読者全員が感じたことだろう。
やはり組織はトップの力量にかかっている。あらためて強く感じたのはこのことだった。
繁栄と衰退は世の常だが、重要なことは、構成員全員が納得できる運営であるべきだということだ。
シャープのこの10年間はそれがなかったように思われる。それだけに現場で頑張っている人たちが気の毒でならない。
こちらもおススメです
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(3) - 2018年12月25日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(2) - 2018年12月20日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(1) - 2018年12月19日