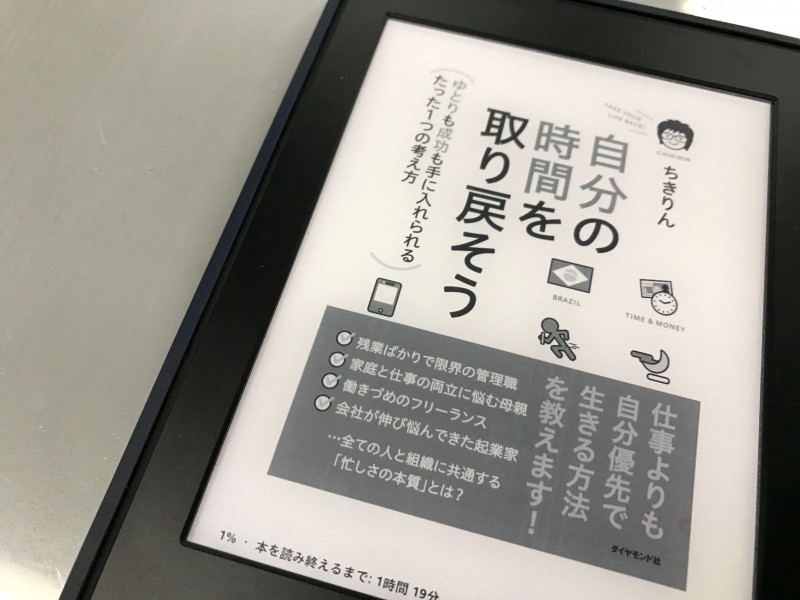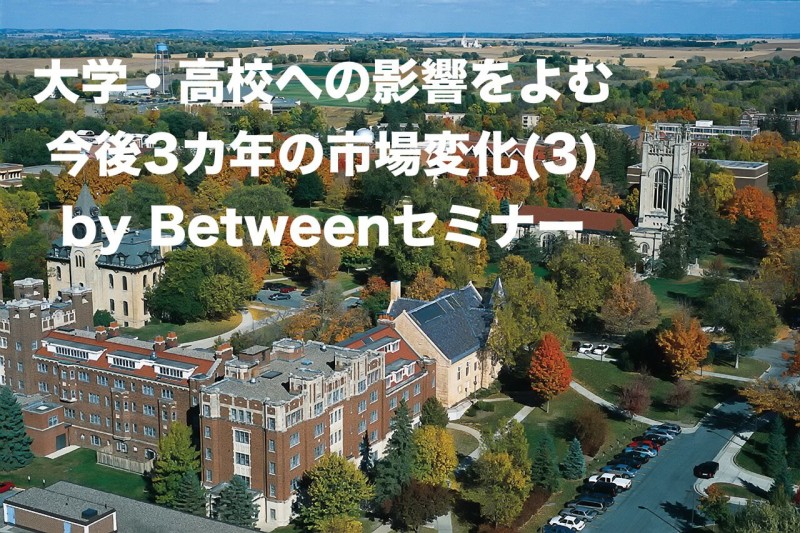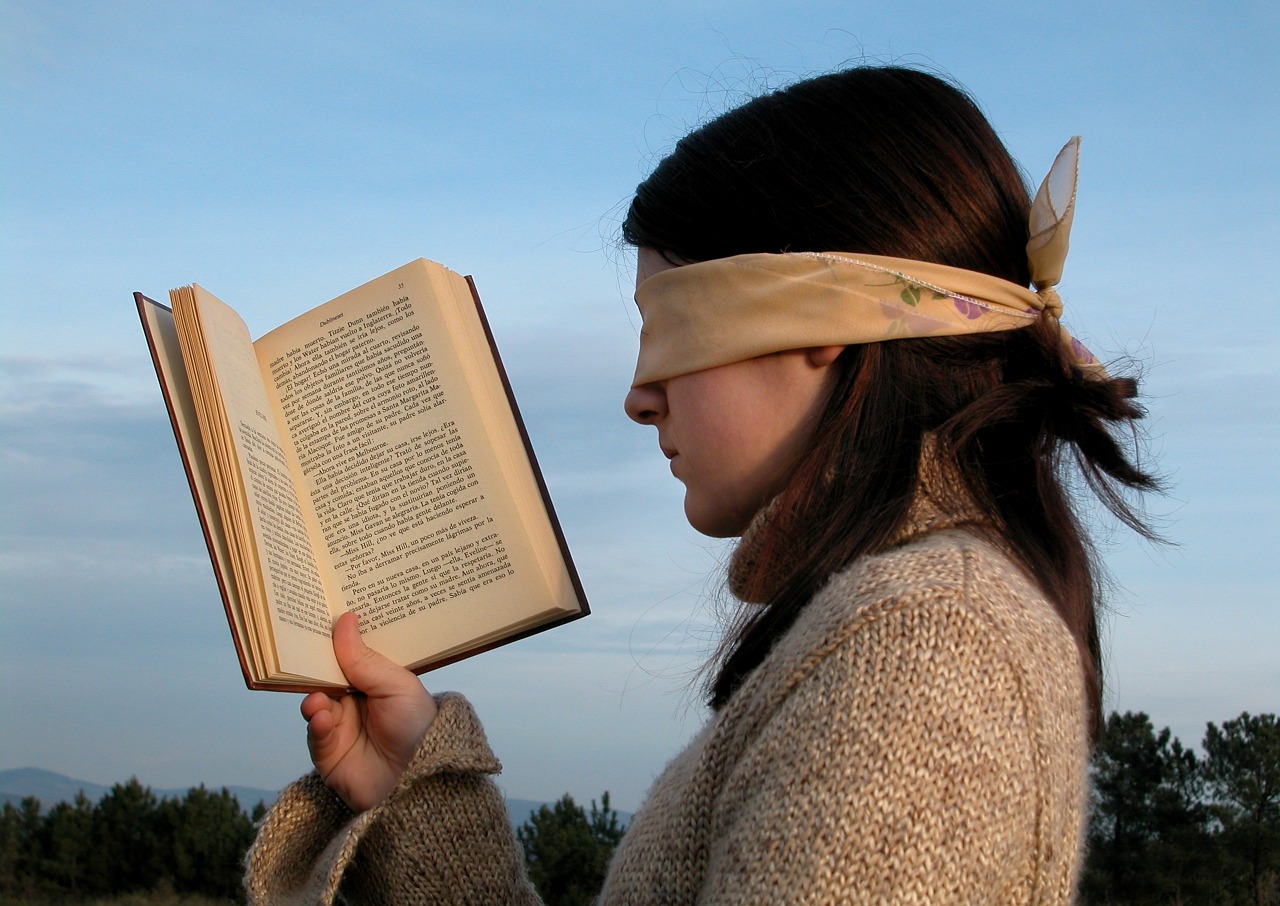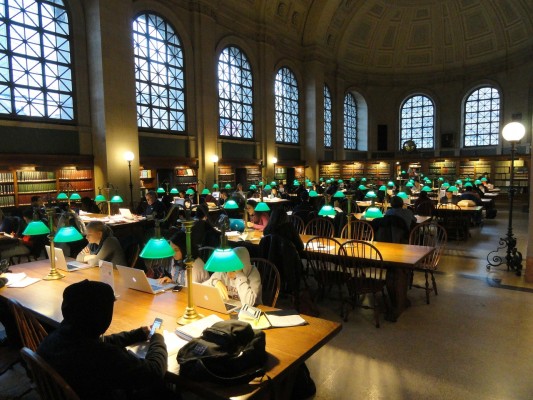このページの目次
はじめに
『自分の時間を取り戻そうーゆとりも成功も手に入れられるたった1つの考え方』ちきりん著(ダイヤモンド社)を読んだ。
本書にも出てくる、いつも「忙しすぎる人たち」には参考になる内容が満載である。生産性を上げるためのヒントを実践していただきたい。
とてもよかったので、シェアしておきたい。
さっそくご紹介しよう。
本書の概要
『自分のアタマで考えよう』『マーケット感覚を身につけよう』に続くシリーズの3冊目である。
ダイヤモンド社の紹介文が本書のエッセンスを言い表わしている。
生産性は、論理的思考と同じように、単なるスキルに止まらず価値観や判断軸ともなる重要なもの。
しかし日本のホワイトカラー業務では無視され続け、それが意味のない長時間労働と日本経済低迷の一因となっています。
そうした状況を打開するため、超人気ブロガーが生産性の重要性と上げ方を多数の事例とともに解説します。
目次
序章 「忙しすぎる」人たち
1 高生産性シフトの衝撃
2 よくある誤解
3 どんな仕事がなくなるの!?
4 インプットを理解する
5 アウトプットを理解する
6 生産性の高め方①
7 生産性の高め方②
8 高生産性社会に生きる意味
終 それぞれの新しい人生
さいごに 〜人生のご褒美〜
参考文献
生産性の重要性
本書のテーマは「生産性を上げること」である。
なぜ働く時間に見合った成果が上げられないのか?
それは考えるのを止め、無思考モードになって目の前の作業に没頭してしまうから。
生産性とは「時間やお金など有限で貴重な資源」と「手に入れたいもの=成果」の比率のことで、希少資源がどの程度、有効活用されているかという度合い。
私がみなさんに生産性を上げようと勧めているのは、まずは自分や家族を傷つけてしまいかねない「多忙すぎる生活」から脱出してほしいからです。
そして「ずっとやってみたいと思っていたけれど、時間がなくて未だにできていないこと」ができる生活に、一歩でも近づいてほしいから。
最後には、やりたいことがすべてできる人生を手に入れてほしいからです。
日本で生産性がもっとも高い人たちは?
今、日本で生産性がもっとも高いのは、働きながら子育てをしているワーキングマザー。
生産性を上げなければと真剣に考えるのは、「そうせざるをえなくなった人だけ」。
生産性を上げる方法
生産性を上げるためにはインプット(時間やお金)を減らせばよい。
具体的には、労働時間を減らす、家事や育児に使う時間を減らす、学生なら勉強時間を減らすことが、生産性を上げるのに役立つ。
まずは働く時間を減らそう
インプットを制限する具体的な方法
その1 1日の総労働時間を制限する
その2 業務ごとの投入時間を決める
その3 忙しくなる前に休暇の予定をたてる
その4 余裕時間をたくさん確保しておく
その5 仕事以外のこともスケジュール表に書き込む
どの仕事にも割り当てない時間をたっぷりと確保し、各仕事は「こんな短い時間ではとても無理」という状態にしてから、「その時間内で終わるやり方」をゼロベースで考える——これが生産性を上げるための秘訣。
無駄な時間を減らすための具体的な方法
その1 「すべてをやる必要はない!」と自分に断言する
その2 まず「やめる」
その3 「最後まで頑張る場所」は厳選する
その4 時間の家計簿をつける
変わり始めたトレンド
「時間が足りない!」と感じているなら、時間の使用記録をとるのが最初の一歩。
高生産性社会に生きる意味
新ビジネス普及の鍵は生産性格差にあり、高生産性シフトが経済成長の新たな源泉になる。
生産性を高めようとしない人は、積極的にそうしようとする人に比べ、自分が本当にやりたいと思うことに使える時間やお金が確保しにくくなる。
個人が生産性の高さを評価しない国では、社会の生産性も上がらない。
大組織に勤める正社員についても、時間を投入することで乗り切るというインプット投入型の働き方からどう脱却するのか、そろそろ真剣に考え始める必要がある。
生産性を上げるメリット
以下の3点が挙げられている。
- いつのまにか成長できていること
- やりたいこととそうでもないことが、明確に区別できるようになる
- 自分の人生の希少資源の使い途に関して、他人の目が気にならなくなる
教育機関の生産性が低くて、授業料が高すぎる
筆者が所属する業界についての指摘である。
- 教育機関の生産性が低くて、授業料が高すぎる。
- 教育機関の生産性が低いのは、IT化やグローバリゼーションが進んでいないから。
- 高等教育機関の生産性が上がり、今、数年かけて教えていることを1年で教えられるようになれば、もしくは、ITを活用して世界中に授業を配信できるようになれば、ひとりあたりの授業料は今よりはるかに安くできる。
- 貧困家庭の子供らが大学進学をするため、奨学金という名の多大な借金を抱えてしまうことが問題になっているが、大学が生産性を上げ、4年分を1年で教えるようになれば、生活費は1年分しかかからず、借金(奨学金)の額も大幅に減らせる。
- お金に余裕のある家庭が、生産性の低い学校に多額の授業料を払うのはともかく、借金までしてあんな生産性の低い教育サービスを買わなければならないなんて、本当に馬鹿げたことだ。
極端な意見もあるとはいえ、耳の痛い指摘である。
これまでの固定概念を覆す、あらたな改革が必要な時代になったようだ。
筆者の経験・実践していること
筆者の場合、セミリタイアの身なので比較的時間の余裕がある。
フルタイムで働いておられる方々とは少々事情が違うことをあらかじめご了承いただきたい。
毎年、年間目標を設定し、それを月から日にドリルダウンしている。
大切なことは、人生の目標・年間目標を達成するために、1日1日を積み重ねていくようにすること(なかなかうまく行かないが…)。
そして、毎朝、手帳にその日のToDoリストをタイムスケジュールを記入している。
毎日のタイムスケジュールをおおよそ決めていて、不規則な生活にならないように心がけている。
その結果、いろいろな用事で頭が混乱するということが、以前と比べると激減している。
フォーカスしているのは、下記に述べるように、「重要だが急がないこと」をじっくりと考える時間を取るようにしていることである。
まとめ
タスクに優先順位を付ける。時間的にできないことはあきらめる。
ひとことでいうと、こういうことになるだろうか。
スティーブン・R. コヴィー博士の『7つの習慣』で強調されているのは、「重要だが急がない仕事をじっくりと考える時間を取る」である。
本書の考え方と共通するものがある。
職業人としてではなく、個人としてどのような人生を送りたいのか、仕事以外では、人生の時間をなにに使いたいのか。今よりはるかに強く、生きる意味について問われる時代がやってくる——それこそが高生産性社会を迎えるにあたって、多くの人が直面する本当の課題なのかもしれません。

- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(3) - 2018年12月25日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(2) - 2018年12月20日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(1) - 2018年12月19日