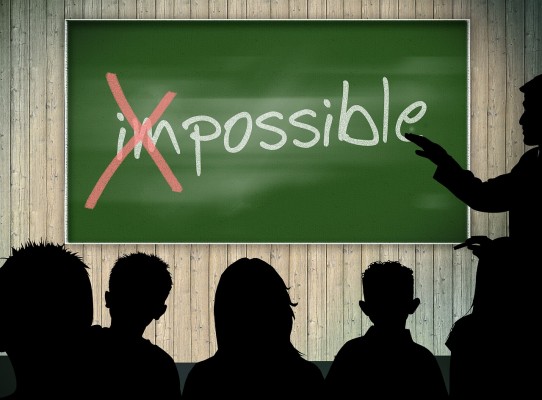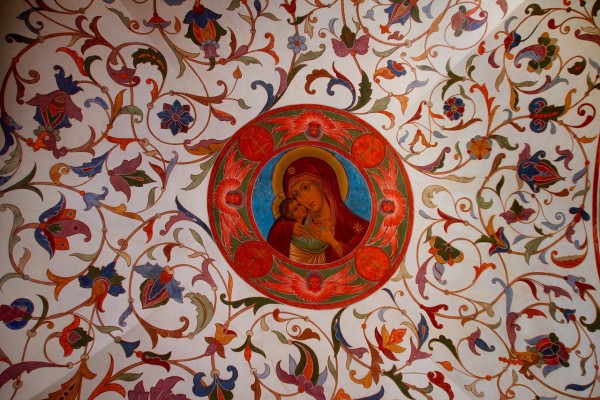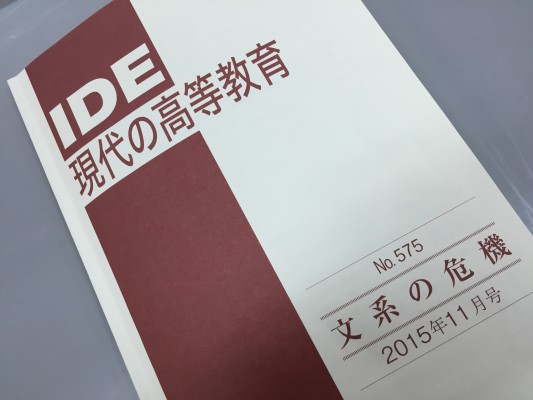はじめに
『戦略的大学職員養成ハンドブック』岩田雅明著(ぎょうせい)の第6章には「大学職員のキャリア紹介 5人の職員たちの、これまでと今、そしてこれから」が収められている。
第一線で活躍されている(こられた)方々の、設問に答える形式の内容になっている。
大学職員の皆さまにぜひ読んでいただきたいと思い、取り上げたしだいである。
3回目の今回は、篠田道夫氏(桜美林大学大学院教授)である。
篠田氏の現在の仕事は、桜美林大学のほか、日本福祉大学学園参与、大正大学特命教授、日本私立大学協会附置私学高等教育研究所研究員、日本高等教育評価機構 評価システム改善検討委員会副委員長、文部科学省 学校法人運営調査委員、中央教育審議会 大学教育部会委員などを務められている。
それではご紹介しよう。
大学職員のキャリア(3)大学職員への熱いエール
大学職員になった経緯、動機
- 母校の職員に日本福祉大学への応募を勧められた。
日本の福祉向上の先頭に立って全学を上げて運動していた同大学に好感を持っていた篠田氏は、
ここで仕事が出来れば、福祉の前進に自分の力が少しでも貢献できるのはないかという思いがあった。
と述懐しておられる。
採用は自校優先でなく実力本位の採用で、徹底した面接試験だったという。
これだけを見ても日本福祉大学の本気度がわかるような気がするのである。
日本福祉大学事務局の3つの発見(創造)
- 卓越したスペシャリスト、担当業務のプロになること
職員の成長、力量形成は現実の業務を遂行し作り変える中でしか身に付かないということ。 - 「研究・教育の目的達成のための事務」
これまでの事務処理から政策業務への進化を意図的に推進することで、事務局業務の内容・水準の高度化を図る取り組み。 - これらをベースとした大学運営参画
特に問題は教学参加。
職員力を付けることと大学運営参画、これは今日の大学職員論の基本を構成する2つの柱、重要な原理である。
大学職員へのメッセージ
大学に、いま求められているものは、「改革の持続」である。
元々意思決定に参画する1票を持たない職員が大学を動かし得るとしたら、その力の源泉は何か。
それは純粋に学生の成長や満足度の向上、大学の発展や目標達成のために献身できる集団として組織され、力を発揮できるかどうかにかかっている。
まとめ
同氏は、教授会の運営に携わった庶務課時代、資料の作成の仕方や議題の整理の仕方に工夫を加え、教授会議長との打ち合わせの際も、自分の意見や新たな提案を行うことで、決定する案件や決定の内容など、大学の方向性が微妙に変化することを感じた。
大学の大きな方向は変えられないにしても、工夫次第では方針づくり等に関与することも可能であり、職員が仕事を通じて大学を動かせるということを実感した、という。
職員力を付けることと大学運営参画。この2つの柱は、
- SDの義務化
- 「事務組織の見直し」
- 「専門的職員」の配置
として、中教審大学教育部会で議論されたことはご存知のとおりである。
同部会の委員が篠田氏である。
今後もお元気に活躍されんことを願ってやまない。

- 作者:岩田 雅明
- 出版社:ぎょうせい
- 発売日: 2016-02-26
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(3) - 2018年12月25日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(2) - 2018年12月20日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(1) - 2018年12月19日