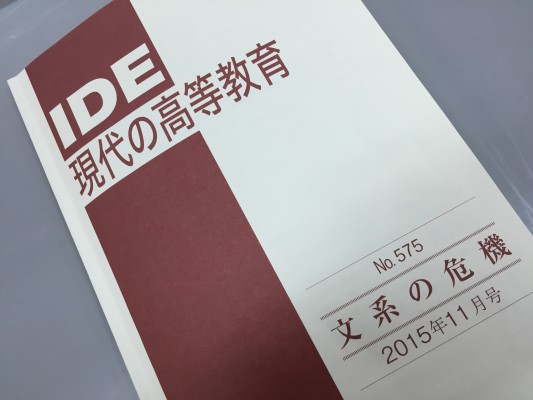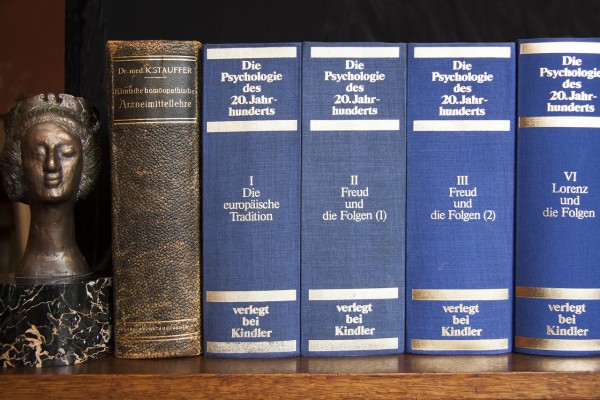人文学の弁明ー国際哲学コレージュの危機から
はじめに
「IDE現代の高等教育」No.575[特集:文系の危機]を読む。
今回は、「人文学の弁明ー国際哲学コレージュの危機から」西山雄二氏(首都大学東京 准教授/フランス思想)です。
私なりにまとめると以下のようになります。
- フランスの国際哲学コレージュという研究教育施設が存続の危機に陥ったが、それを救ったのは世界18カ国に翻訳された請願書だった。
- フランスの事例からみる文系の危機の論点は、1.選択と集中による急速な大学改革の潮流、2.反知性主義的な風潮、3.人文学の社会的な実践、4.国際的な連帯の4点。
それではご紹介しましょう。
国際哲学コレージュの危機
- 「脱構築」で知られるフランスの哲学者ジャック・デリダらが1983年、パリに創設した国際哲学コレージュ。伝統的な大学制度では十分に研究できない新たな主題や領域のために、大学とは一線を画する「思考の実験場」として設立された。
- 2014年には閉鎖寸前の深刻な危機に追いやられた。
- 危機を打開しようと、請願書が起草され、18カ国に翻訳された。
- 請願書をもとに国際的な規模で署名活動が始まり、1週間で10,000筆を超えた。
- 各方面からの支援が功を奏して、公開書簡を出していたオランド大統領から、存続確保の返信がコラージュに届いた。
フランスの事例からみる文系の危機の論点
- 選択と集中による急速な大学改革の潮流
政府主導の大学改革は往々にして大学の体制順応主義的な体質を助長し、その批判的精神を減退させることで、学問の重要な生命力であるその独立性を萎縮させかねない。 - 反知性主義的な風潮
文系の危機は近年の反知性主義の社会的文脈で理解する必要がある。反知性主義が社会に浸透すればこそ、政治・経済的趨勢による教養の軽視が後押しされる。昨今の反知性主義の特徴は知性への無関心や怠惰ではなく、一定の知的な振る舞いによって積極的に相手を攻撃する点にある。あくまでも知性を放棄することなく、ポピュリズムやレイシズムと結託する形で一定のタイプの知が告発される。これを回避するには、伝統的な口調で教養主義の尊さを説くだけでも、大衆迎合的な仕方で人文知のポピュラー化を図るだけでも不十分で、ここに今日の文系の隘路がある。 - 人文学の社会的な実践
大学の制度内だけでなく、人文学は大学の外ないしはその余白において、研究教育活動を柔軟に展開する可能性がある。人文学はその厚みのある境界線を活性化させる自由度がある。 - 国際的な連帯は重要
文系の危機は世界的な現象であるがゆえに、国際哲学コレージュ存続の署名活動が示したように、国際的な連携は有効。どこかの卓越した研究教育機関が理不尽な危機に曝されることがあれば、国内外からの支援が広がることが望ましい。日本の文系組織に往々にして欠けているのは、危機の際の国際的な連帯ではないだろうか。
まとめ
課題は2点あるように感じました。
1点目は、上記のような反知性主義をどう回避するかです。
「政治・経済的趨勢による教養の軽視」はますます広がっているように思えてなりません。
経済的に余裕ができれば精神的にも余裕が生まれ、本来の知性が大切にされるようになるのかもしれないと感じたりもします。そうだとすれば、必要なことは、景気の浮揚であり、マクロな視点からいえば「経済成長」に代わる国家の目標を確立することなのかもしれません。
2点目はタイトルにも付した「国際的な連携」です。
日本の教員や学会がどの程度世界の学会とつながりがあるのかは知らないのですが、上記のように世界中からの請願書があれば、今回の危機もすこしは変化があったのかもしれません。
⇒第10回:地方国立大学に文系学部は必要かを読む。
【目次】文系の危機―「IDE現代の高等教育」No.575 2015年11月号を読む
The following two tabs change content below.

大学職員ブロガーです。テーマは「大学職員のインプットとアウトプット」です。【経歴】 大学卒業後、関西にある私立大学へ奉職し、41年間勤めました。 退職後も、大学職員の自己啓発や勉強のお手伝いをし、未来に希望のもてる大学職員を増やすことができればいいなと考えています。【趣味】読書・音楽(主にジャズとクラシック)・旅 【信条】 健康第一であと10年!
最新記事 by 瀬田 博 (全て見る)
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(3) - 2018年12月25日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(2) - 2018年12月20日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(1) - 2018年12月19日