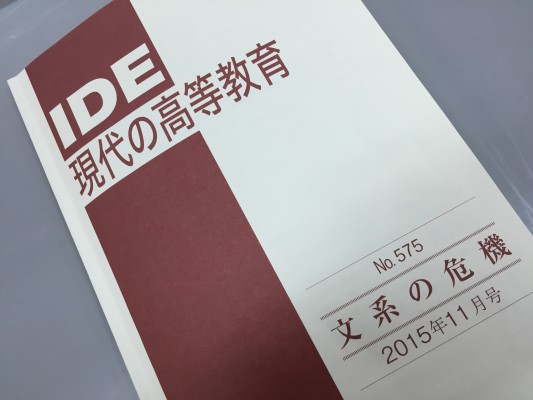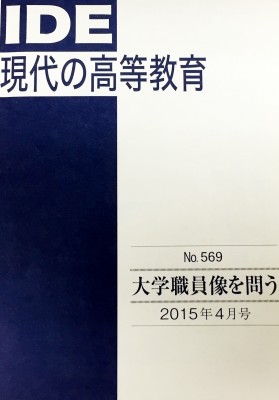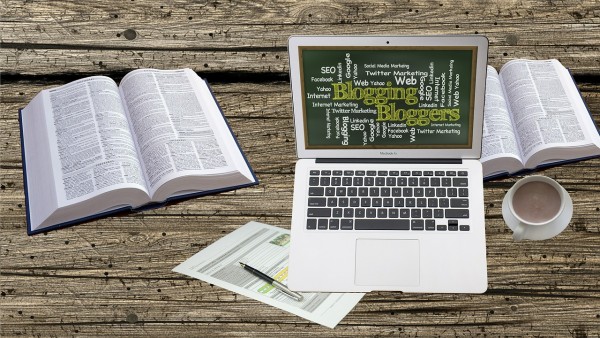2回目の今回は、「逆風化の文系学部とその役割」石 弘光氏(一橋大学名誉教授/財政学)です。
述べられているポイントは、以下の5点です。
- 成長戦略の一環としての大学改革の議論には違和感を感じる。
- 運営交付金を削減し、それを競争的資金で補うというデュアル・サポートは改めるべき。
- 研究費配分に自然科学、人文社会科学両分野で同じ指標が用いられると、文系が不利になる。
- 自然科学と人文社会科学のバランスを取り、研究教育を進める必要がある。
- 文系大学・大学院の問題点を改善し、組織の廃止、見直しを行うべき。
それではご紹介します。
●●●
成長戦略に取り込まれた大学改革
- (文系学部が軽視される要因は)目下進められている大学改革がアベノミクスの第3の矢である成長戦略の一環として議論されていることによる。
- 政治家と経済人が主体となる産業競争力会議の議論は、これまで大学関係者に主導された視点とは自ずから異なり、違和感を禁じ得ない。
- 経済界を中心に大学にも専ら「社会に役に立つ」視点が強調されるが、これこそ職業訓練学校に言うべきことである。
- アベノミクスに取り込まれた大学改革の現状では、将来わが国の研究教育に禍根を残すことになろう。
デュアル・サポートと競争的資金
- 国立大学が法人化され11年経過する中で、文系学部に不利な環境が自ずから醸成されてきた資金配分の制度がある。
- 基盤的経費を賄う運営費交付金と研究費のために充当される競争的資金の2つのルートで行われてきた。しかし現在、このデュアル・サポートの綻びが目立っている。
- 自然科学系の学部を持ち競争力のある大学とそうでない大学に、競争的資金の獲得に当たり二分化されてきた。
- 運営費交付金を定期的に削減しそれを競争的資金で補う、というデュアル・サポートを改めるべきである。
- 競争的資金の一部を運営費交付金に回し、大学の基盤経費をより安定的に支給するべきだろう。
異質な評価方法
- 研究費の配分が行われる際に研究毎に評価が行われるが、自然科学、人文社会科学の両分野で同じ指標が用いられている点に問題がある。
- 多量に論文を作成・公表しやすい自然科学と正反対の性格を持つ人文社会科学とで同じように論文数・論文被引用数を基準に、研究成果が評価されその数量だけで優劣が競われている。
- 明らかに、文系の学問分野が不利にならざるをえない。
学問的価値の再認識
- 多様な価値観を尊重し、物事に対する洞察力を深めそして自らの人格形成に努めるために、主に人文社会科学に立脚した高い教養こそが不可欠になってくるのだ。
- 大学においては、自然科学と人文社会科学のバランスを取り研究教育を進める必要がある。
- 大学ではすぐに役に立たなくても、将来の多様な人材育成に繋がる人文社会科学の学問は欠かせないとするのが、大学関係者の思いといえよう。
むすびー大学の責任
- まだまだわが国の文系学部・大学院では問題が多い。最低でも次の3点の改善が必要だろう。
①カリキュラムの組み方、授業や試験のやり方、成績評価などで文系学部が以前学生に甘すぎる。
②大学はあくまで研究中心と、教育にかまける教師が依然多い。
③文系の博士号の取得が依然低い。 - 大学は自ら学内組織のあり方を再検討し、教員の配置替えも含み困難な問題もあろうが、もし必要とあれば、断固組織の廃止・見直しを行うべきである。
●●●
人文知が必要であることは論をまたないことです。問題は、これまで学生がそれを大学生活で得られてきたかどうか、ということではないでしょうか。
⇒第3回:大学と産業の距離についてを読む。
【目次】文系の危機―「IDE現代の高等教育」No.575 2015年11月号を読む
The following two tabs change content below.

大学職員ブロガーです。テーマは「大学職員のインプットとアウトプット」です。【経歴】 大学卒業後、関西にある私立大学へ奉職し、41年間勤めました。 退職後も、大学職員の自己啓発や勉強のお手伝いをし、未来に希望のもてる大学職員を増やすことができればいいなと考えています。【趣味】読書・音楽(主にジャズとクラシック)・旅 【信条】 健康第一であと10年!
最新記事 by 瀬田 博 (全て見る)
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(3) - 2018年12月25日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(2) - 2018年12月20日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(1) - 2018年12月19日