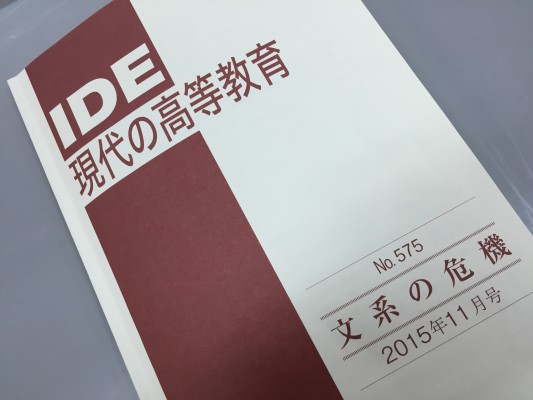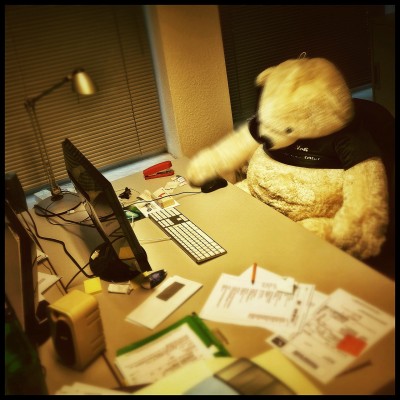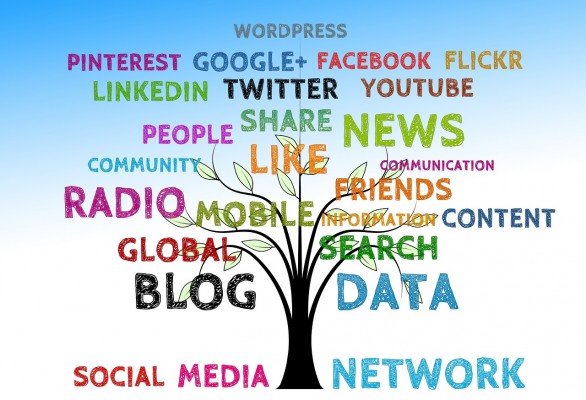今回は「文系の危機と教養教育」野家啓一氏(東北大学 総長特命教授/哲学)です。
主なポイントは以下のとおりです。
- 国立大学法人の組織・業務見直しは、一連のネオ・リベラリズム(新自由主義)に基づく教育改革の総仕上げと位置づけることができる。
- 文系大学院の再編は必至であった。
- 今回の今回の通達は、ピンチを文系の存在意義を再確認し宣揚する「文系のチャンス」として捉え直すべきもの。
それではご紹介します。
●●●
1.学術会議シンポジウム
- 7月31日、日本学術会議第一部(人文・社会科学)の主催で公開シンポジウム『人文・社会科学と大学のゆくえ』が開催された。200人強が限度の講堂に400人近くも聴衆が集まるなど前代未聞のこと。
- 今回の通知は突然なにもないところから降って湧いたものではない。
- 昨年(2014年)9月に「国立大学法人評価委員会」から出された報告書中に、同様の文言は盛り込められていた。
- 本年4月には下村文部科学大臣名で『イノベーションの視点からの国立大学改革について』が出された。
- 文系分野をターゲットとした組織の見直しが「ミッションの再定義」を軸とした第3期の中期目標・中期計画と密接に連動している。
- 布石は着々と打たれてきたのであり、すでに外堀は埋められている。
- 既得権益の擁護と受け止められることを避けるために、今回の事態がどのような歴史的・社会的文脈のなかで生じたのかをもう一度確認しておく必要がある。
2.新自由主義による大学改革
- 今回の国立大学法人の組織・業務見直しは、一連のネオ・リベラリズム(新自由主義)に基づく教育改革の総仕上げと位置づけることができる。
- 改革の第一段階である「大学設置基準の大綱化」は教養部の瓦解をもたらした。
- 第二段階は1990年代後半に推進された「大学院重点化」。教育内容の質的向上を伴わないまま量的拡大を目指して進められたため、人文・社会科学分野には大きな禍根を残すことになった。
- 最終段階は「国立大学法人化」の施策。行政改革会議による国家公務員削減策の一環として立案されたものであり、主目的は国立大学教職員の非公務員化にこそあった。
- 今回の組織・業務見直しの通達は、寝耳に水のことではなく、一連の新自由主義的大学改革の流れを背景として考えられねばならない。
3.大学院の教養教育
- 文系大学院の再編は必至であった。
- 文系大学院で学位をとった人材が、終了後に国連や世界銀行などの国際機関で活躍できるような教育システムを導入せねばならない。
- 博士前期課程(修士課程)に関しては、社会人再教育にもっと門戸を開くべき。社会人再教育のコースを充実させることなしには、現在の水膨れした定員を満たすことはおぼつかない。
- 博士後期課程(博士課程)については、選抜を厳格にしてスリム化すべき。余剰人員は「大学院の教養教育」に振り向けるべき。
- 教養とは「社会の中での自己認識」を行う知識と能力。
- 今回の通達は、むしろピンチを文系の存在意義を再確認し宣揚する「文系のチャンス」として捉え直すべきもの。
●●●
感想
「新自由主義による大学改革」という指摘から、唐突に大学院の改革へと話題が移っていることに少々戸惑いました。あるいは私が誤読しているのかもしれませんが。
企業がさほど評価しない(あるいは処遇に苦慮する)と言われる文系の修士号ですが、いま以上に門戸を広げてどれほど志願者が集まるかは疑問です。まして社会人となれば、いろいろな意味でむずかしいのではないでしょうか。企業の処遇等の変化がまず前提となると考えます。
⇒第7回:反知性主義的空気と大学改革を読む。
【目次】文系の危機―「IDE現代の高等教育」No.575 2015年11月号を読む
The following two tabs change content below.

大学職員ブロガーです。テーマは「大学職員のインプットとアウトプット」です。【経歴】 大学卒業後、関西にある私立大学へ奉職し、41年間勤めました。 退職後も、大学職員の自己啓発や勉強のお手伝いをし、未来に希望のもてる大学職員を増やすことができればいいなと考えています。【趣味】読書・音楽(主にジャズとクラシック)・旅 【信条】 健康第一であと10年!
最新記事 by 瀬田 博 (全て見る)
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(3) - 2018年12月25日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(2) - 2018年12月20日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(1) - 2018年12月19日