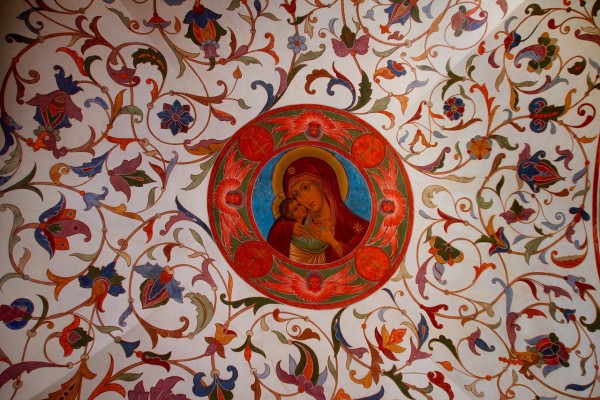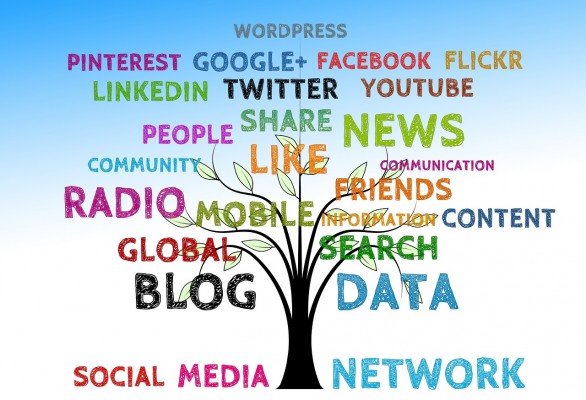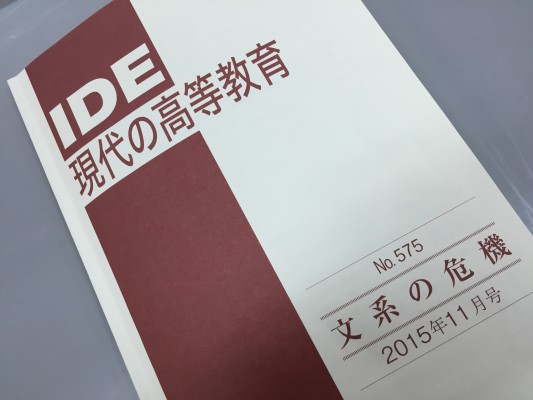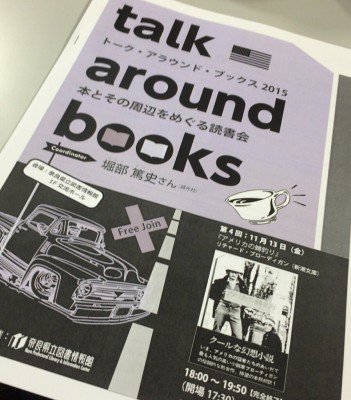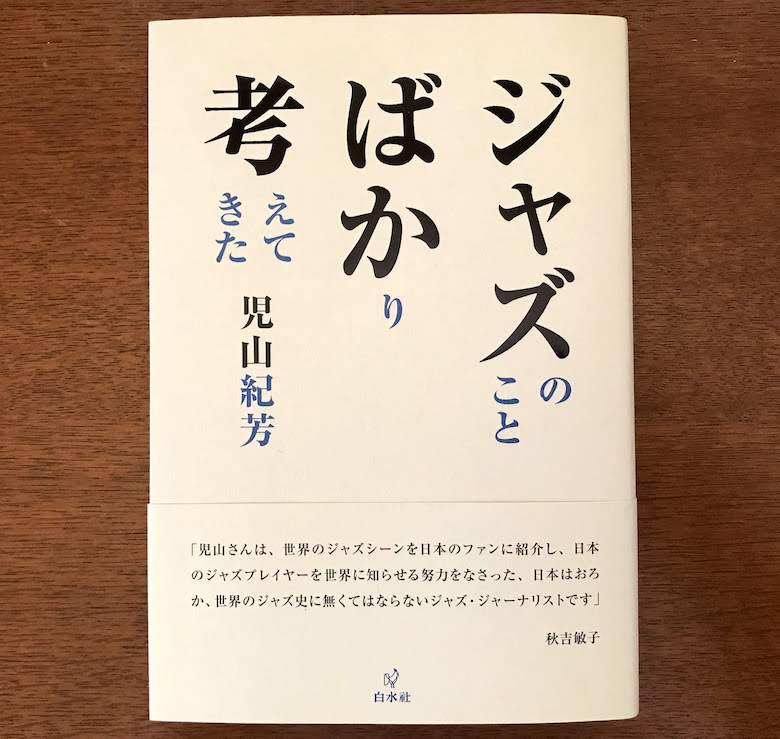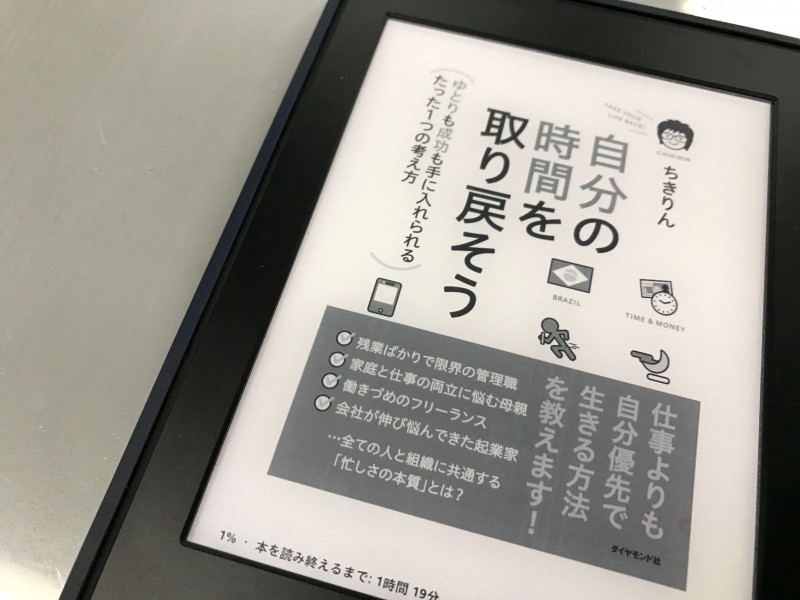『知的資本論 すべての企業がデザイナー集団になる』 増田宗昭(CCCメディアハウス)
これから必要とされるのは「知的資本」
これは面白かったです。読んでいてワクワクし、自分も何かやらねば、と思わせてくれる本はなかなかありません。このことは、ほかならぬ著者自身がそういう人生を送っていることを意味するのだと思います。

- 作者:増田宗昭
- 出版社:CCCメディアハウス
- 発売日: 2014-10-09
デザインとは提案を可視化すること
デザインとは、頭の中にある理念や想いに形を与え、顧客の前に差し出してみせる作業。
一般的に思い出す美術的なデザインではなく、企画力とでもいうべきものですね。
提案を可視化する能力がなければ、つまりデザイナーにならなければ、顧客価値を増大させることなど、できはしない。
つまり提案を可視化する能力、ということです。
一人ひとりの顧客にとって価値の高いものを、探し出し、選び抜いて提案してくれる者。それが現在の成熟社会においては、より大きな顧客価値を生み出し、そして競争において優位に立てる存在。
以前one to oneマーケティングという言葉がありましたが、マスを対象にモノやサービスをただ提供しているだけではダメだということです。
そのためには一人ひとりについてのデータが必要となります。
これから必要とされるのは、”知的資本”。
知性と言い換えてもいいかもしれません。知識社会においてルーティン業務だけをしてビジネスが成立するはずがありません。 これも同じ意味です。
これまで考えられてきたような資本、つまり財務的な資本の大小が、企業活動の成否を決定する時代は過ぎ去り、社内に”知的資本”がどれほど蓄積され、そして発揮させられるかが企業の推進力を左右する時代になる。
知的資本の時代とは、すなわち並列型の組織の時代 。
これが個人的にはもっとも興味深い指摘でした。
トップダウンもボトムアップも直列型の組織の言葉ですが、もう限界にきているように思います。アメとムチなんていうのもそうですね。
では並列型の組織の基礎となるものは何でしょう。
並列に並んだ、自分も含めた一つひとつの装置を結び合わせるのが、求心力を備えた理念。
求心力がなければバラバラになっちゃいますもんね。
そのことも大事ですが、分かりやすい理念は組織にとって重要だとあらためて感じます。
でっちあげた形だけのものではなく、構成員全員がそうしたいという理念。
これがないから組織を直列にしたり、アメとムチで人を動かそうとするのではないでしょうか。
しかし、並列型の組織には厳しい側面もあります。
ヒューマンスケールの組織、クラウド型の並列の組織の中では、上司―部下という直列のラインの中に身を隠すことはできない。会社の知的資本であるデータベースを用いて、自由に企画を立てる。それしかないのだ。
これは現状維持型、ルーティン・ワーク型の人たち(ほとんどの組織人)には厳しい注文でしょう。
その反面、若い人たちには歓迎されると思いますが。
これから、コンビニエンスストアでも巨大モールでもないリアル店舗が、ネットに対して優位性を持てるとすれば、それは居心地よさの提供という面においてだろう。
実店舗における居心地よさの提供。
ショップだけではなく、これはどんな業種にもいえるのではないでしょうか。
顧客にとって居心地のよい雰囲気を提供する。まさに成熟社会におけるサービスの定義だと思います。
ブランドとかデータベースとか、あるいは豊かな見識と経験を備えたコンシェルジュとか、そういったバランスシートに載らない知的資産のほうが、これからのビジネスでは死命を握る要素となる。
定量分析と定性分析。
むずかしい問題です。
しかしここではバランスシートに載らない知的資産、とあります。
カネで勘定できないモノ(知的資産)が大事だという意味では非常によくわかります。
自分が努力しなければならないこと
# デザイン力を磨く 頭の中にある理念や想いに形を与え、顧客の前に差し出してみせる作業 提案を可視化する能力
# キュレーターになって顧客価値を生み出し、競争優位を獲得する 顧客にとって価値の高いものを探し出し、選び抜いて提案する。
# 居心地良さの提供 リアル店舗の優位性は、居心地良さの提供
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(3) - 2018年12月25日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(2) - 2018年12月20日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(1) - 2018年12月19日