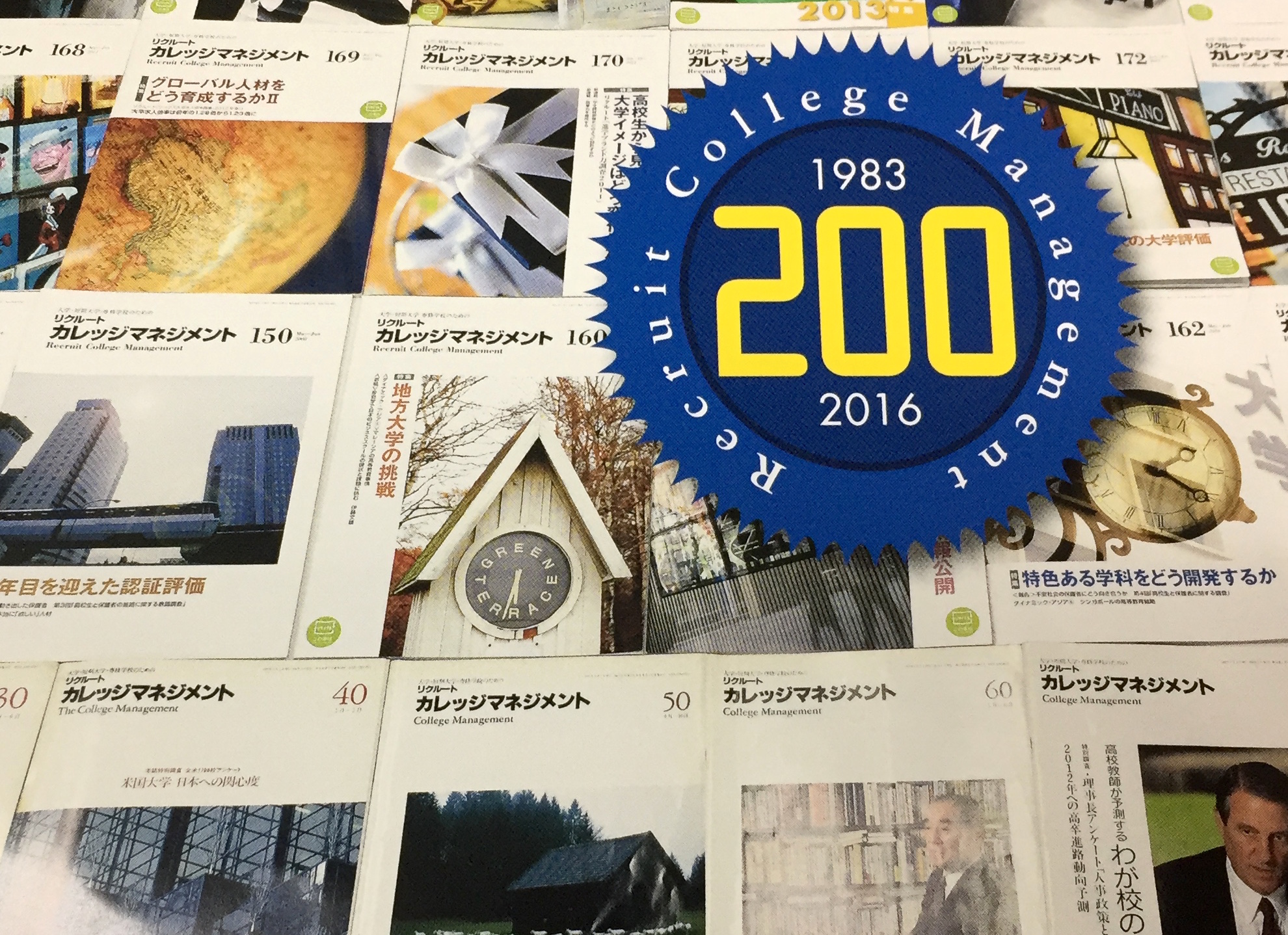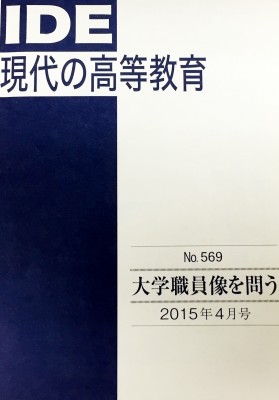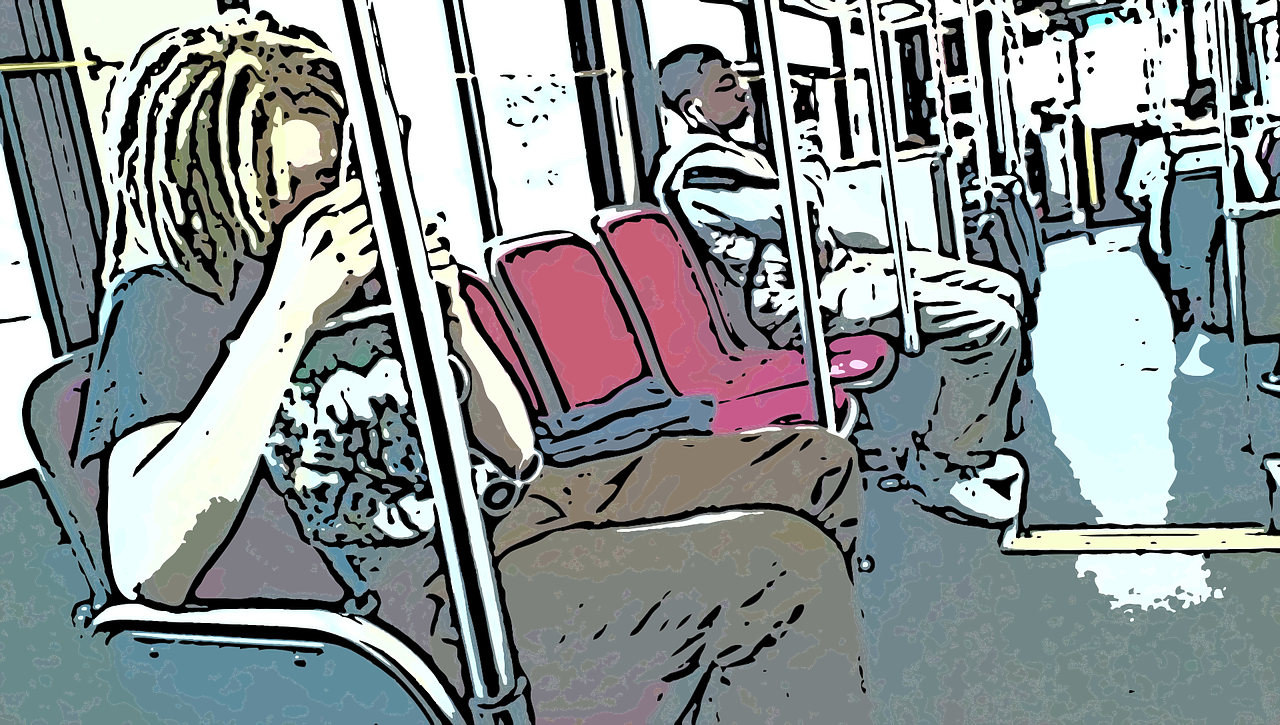苅谷剛彦氏「スーパーグローバル大『外国人教員等』 実態は経験浅い日本人」
苅谷剛彦「高等教育の“日本病” グローバル化に乗り遅れた日本の大学」(1)
苅谷剛彦「高等教育の“日本病” グローバル化に乗り遅れた日本の大学」(2)
日本の大学:危機を越えて―刈谷剛彦氏の講演から
このページの目次
「カレッジマネジメント」創刊200号記念特集
「カレッジマネジメント」が200号を迎えた。1983年の創刊から、ことしで33年目となるそうだ。心から敬意を表したい。
その特集号では、200号記念特集として、潮木守一氏の巻頭エッセイにはじまり、トップマネジメント座談会「今後の大学における学長の責務とは」、そして苅谷剛彦氏の特別寄稿が掲載されている。
また、今号の特集として「進学ブランド力調査2016」が掲載されており、盛りだくさんの内容となっている。
ここで取り上げるのは「オックスフォードから見た日本の大学」と題した苅谷氏の論稿である。
苅谷剛彦氏は現在、オックスフォード大学社会学科及びニッサン現代日本研究所教授。
同氏はここで、日本の大学改革の核心部ともいうべき点について、わかりやすく指摘しておられる。
日本の大学の課題に焦点を当て、筆者なりにまとめたものを以下ご紹介しよう。
オックスフォードから見た日本の大学
大学と国家とのパワーバランスの歪み
近年の日本の大学を見ると、国立大学は言うに及ばず、私立大学においても文科省の政策に右往左往している印象を受ける。
国は財政支援を競争的資金にウェイトを掛けることで政策誘導をしようとしている。だが、そこでの政策自体が十分に練られたものには見えない。
にも拘わらず、大学はわずかな資金獲得をめぐってその政策に左右されている。あるいは改革の実はともあれ、形式主義的ともいえる改革を志向しているように見える。
社会からの信頼基盤の弱さ
昨年6月の文科省による「文系学部廃止論」騒ぎにも、日本の大学と国家とのパワーバランスの歪みが現れている。原因となった文科省の「通知」の真意がどこにあったかはおくとして、騒然となるだけの背景は、近年の日本の「国家と大学」のパワーバランスの変化にあった。
ある意味、大学側の抵抗力、あるいは独立性の弱体化を示す出来事。
日本の大学と国家とのパワーバランスが、後者に傾きつつある背景には、大学の財政基盤が欧米の有力大学に比べ盤石ではないことに加え、社会からの信頼基盤の弱さにもある。
文系学部廃止論がまことしやかに受け止められたのも、文系学部が社会の「役に立ってない」という暗黙の前提が社会の側にあり、そこを衝かれたから。
すぐに役立つ教育をという判断基準自体に疑義を呈することもできるが、そうした主張に説得力を与えるところまで、日本の大学は特に教育面でその実力も実績も社会で受けいれられていなかったのかもしれない。
新しい入試制度への対応―ここでも大学への信頼の希薄さが
日本では入試に論述式や面接を入れると「客観性」や「公平性」が損なわれるのではないかと心配される。それも見方を変えれば、大学への信頼の希薄さの表れといえる。
講義中心の日本の大学の学習場面を見ると、そこでは公平さや客観性を求めるために、個々の学生の顔を見えにくくする学習が主流となる。入試もしかり、である。主観性を排することが公平とされ、受験生は受験番号と試験の得点によって記号化される。
入試改革での面接導入への危惧は、このような社会心理と関係している。
アクティブラーニングは主体的な学習者を生むか?
アクティブラーニングが奨励されるようになった。授業への学生の主体的な参加を促すことが、主体的な学習者を生み出す方法だと見なされている。そのための授業の工夫が教員にも求められている。
講読文献や論文執筆等の点で学習への負荷が小さいままであれば、どんなに表面的には積極的に授業に参加する学生が増えても、そこで育成される思考力が深いものになるとは限らない。行動として目に見える一見主体的な学習への参加が、主体的な学習を生み出す保証はない。
これまでのように、学生達に学習の負荷を大きく掛けないカリキュラムの構造(週に十何種類もの授業を履修!)を変えないままであれば、参加型学習のススメは表層的な活動主義に終わる可能性が高い。
流行の協働学習のような試みも、個の自立より集団への同調・埋没を誘うだけになりかねない。
まとめ
筆者なりにまとめれば、課題はつぎの2点になる。
- 教育面で、実力も実績も社会から信頼されるようになること。
- 学生に学習の負荷(購読文献や論文執筆等)を大きくかけること。週に十何種類もの授業を履修するカリキュラムの構造を変えること。
近年、教育の質充実が叫ばれ、「入口」(偏差値)より「出口」(在学中の教育成果)での評価を重視されるようになったのは喜ばしいことだ。
だが、その結果、授業外学習時間が増えたということは聞かない。
また、FD関連の研究会の「お知らせ」を見ると、「授業方法」についてのものばかりである。
大学人のすべてが、上記のことを「大学改革」のミッションにするべきではあるまいか。

グローバル化時代の大学論2 – イギリスの大学・ニッポンの大学 – カレッジ、チュートリアル、エリート教育 (中公新書ラクレ)
- 作者:苅谷 剛彦
- 出版社:中央公論新社
- 発売日: 2012-10-09
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(3) - 2018年12月25日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(2) - 2018年12月20日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(1) - 2018年12月19日