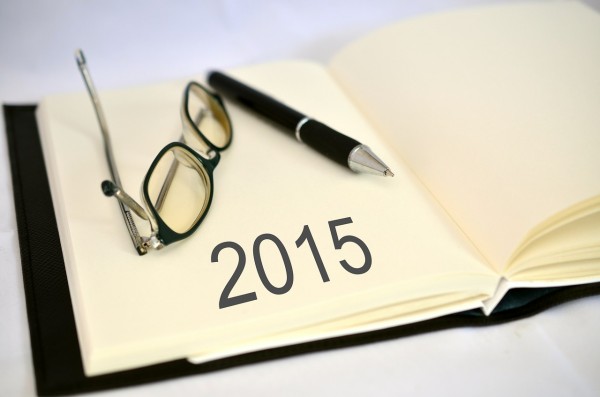今回は苅谷剛彦氏の論説をご紹介します。
要約
高等教育のグローバル化と日本の高等教育について、次のように指摘しています。
- グローバルな競争から大きく立ち遅れた日本の大学の脆弱さ
- 1980年代までの「成功体験」から抜け切れない「日本病」ともいえる姿
大学の問題点
- (量的拡大が)私立大学の拡張を通じて達成されたため、家計の所得水準によって進学機会は経済的な制約を受け続けた。
- 高等教育の拡大が教育の質の低下を伴って進んだ。
具体的には、
- 人件費を抑えるために大人数での講義形式の授業が多くなる。受講生が多くなればきめ細かな学生への指導もフィードバックも難しい。
- 日本の大学とは授業中でしか学ばない所
- ほとんどの授業は学生にリーディング・アサインメント(授業前の参考文献の読み込み)を課さない。
- 一定数の入学者数を確保するためにも、学生たちの就職活動を奨励こそすれ、それを妨げることはできない。
- 厳しい成績評価をして、退学者を出すことも難しい。
という状態であり、これらは、私立大学の多くが、学生の授業料収入に依存しているから。
企業の問題点
これまでは、
- チームワークを通じた協働によって高い生産性を達成する仕組み
- 問われたのは、OJTを通じて効率的に学習できるトレーナビリティ(訓練能力)
であったが、グローバル化はこの仕組みを揺るがしつつある。
上記の仕組みは、以下の前提条件のもとに機能していた。
- 大企業と男性を中心に、安定した雇用機会を持続的に提供できる限りで有効に働くもの
- 国内の雇用市場を前提にしていた
- 少しでも良い大学に入学しようとする競争が学生たちに学習のインセンティブを与えることを前提に成立していた
他の先進国では大学教育での人材育成の場が大学院レベルにシフトしている。教育期間を延ばし、教育の内容もより高度にするグローバルな競争が始まっているのに、日本の大学と企業は4年間の教育さえ十分確保できない。能力やスキルの絶対的な高さが求められる時代に、その面で明らかに劣化が起きている。しかもそれを分かっていてもこれまでの仕組みを変えることができない。
それでは、今後大学は、企業は、どう変わればいいと苅谷氏は述べておられるのでしょうか。それを次回にご紹介します。
About Me
私の自己紹介はこちらです。
SNS
■Twitter:@starofuniv
■Facebook:setahiroshi
The following two tabs change content below.

大学職員ブロガーです。テーマは「大学職員のインプットとアウトプット」です。【経歴】 大学卒業後、関西にある私立大学へ奉職し、41年間勤めました。 退職後も、大学職員の自己啓発や勉強のお手伝いをし、未来に希望のもてる大学職員を増やすことができればいいなと考えています。【趣味】読書・音楽(主にジャズとクラシック)・旅 【信条】 健康第一であと10年!
最新記事 by 瀬田 博 (全て見る)
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(3) - 2018年12月25日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(2) - 2018年12月20日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(1) - 2018年12月19日