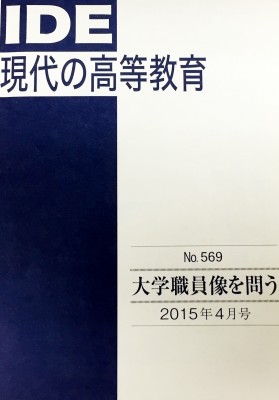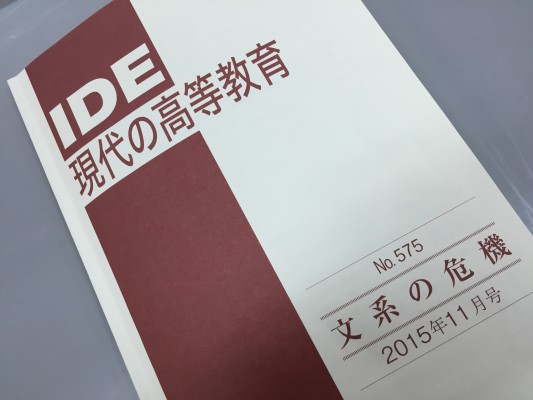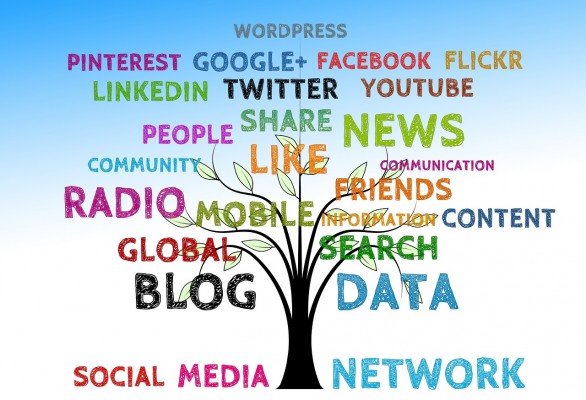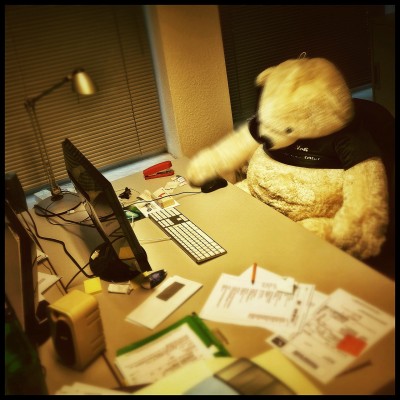「大学職員に望むこと―国立大学学長の視点から」高田邦昭(群馬大学長/解剖学、細胞生物学)
今回は国立大学からの寄稿です。
要点
2.国立大学法人への移行に伴う事務職員像の変化
- 文部科学省人事で異動する幹部職員にとっても、文部科学省(の人事担当者)がどう考えるかが重要な行動の指針だったものが、今働いている大学を発展させるにはどうすれば良いかという視点へと変わってきた。
- 幹部職員の任命自体も、大学採用の生え抜きからの昇進の道が開かれ、各国立大学法人でその育成が進んでいる。
- 「今居る大学をどう発展させるか」という視点が、一人ひとりにどれだけ浸透しているかが、大学発展の底力になっている。
3.教員と事務職員の良い関係
- これからますます多岐にわたる大学内の課題に対し、教員と事務職員とがお互いをリスペクトしながら、それぞれの得意とするところを持ち寄って協働し、知恵を出しあい、解決して行くことが求められている。
- 従来の教員と事務職員との境界の職種も生まれつつあり、大学の教職員像も大きく変わっていく。
4.大学幹部職員に望むこと
- 課題そのものを解決する方策を提案したり、決断することが求められる。
- 広い視野と経験を活かして知恵を出し、大学のためにはどのような解決策があるのか、複数のオプションとそれぞれの得失とを、役員・学長に提示することが求められている。
広い視野を持った幹部職員の存在は、これからの大学運営には必須。
5.おわりに
- 学生、卒業生、社会の声に謙虚に耳を傾け、教員と協働して大学を良くしていくために知恵を出す事務職員が求められている。
変わりつつある職員
国立大学法人の職員も変わってきているようです。上記2でそれは窺うことができます。
幹部職員に求められているのは、広い視野と経験であり、課題を解決する方策を提案し、決断することと、解決策を出し、複数のオプションとその得失とを上層部に提出すること、とあります。
これらは従来型の職員があまりやってこなかったことではないでしょうか。その理由はとにかくとして、課題解決型の人材がここでも求められています。
問われる育成・活用方法
国立大学法人は、私学と異なり潰れることはないにしても、理系シフトへの対応に不安な教職員も多いのではないかと思います。そういったなかで、これまでにはなかった活躍をする近未来型の職員も多く出てくるのでしょう。
幹部職員についての言及が多かったのですが、「従来の教員と事務職員との境界の職種」が現在注目されている高度専門職になるのではないでしょうか。職種と雇用形態の多様化がますます進むなかで、職員をどう育成し、活用していくかということが、設置形態を問わずあらためて問われています。
The following two tabs change content below.

大学職員ブロガーです。テーマは「大学職員のインプットとアウトプット」です。【経歴】 大学卒業後、関西にある私立大学へ奉職し、41年間勤めました。 退職後も、大学職員の自己啓発や勉強のお手伝いをし、未来に希望のもてる大学職員を増やすことができればいいなと考えています。【趣味】読書・音楽(主にジャズとクラシック)・旅 【信条】 健康第一であと10年!
最新記事 by 瀬田 博 (全て見る)
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(3) - 2018年12月25日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(2) - 2018年12月20日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(1) - 2018年12月19日