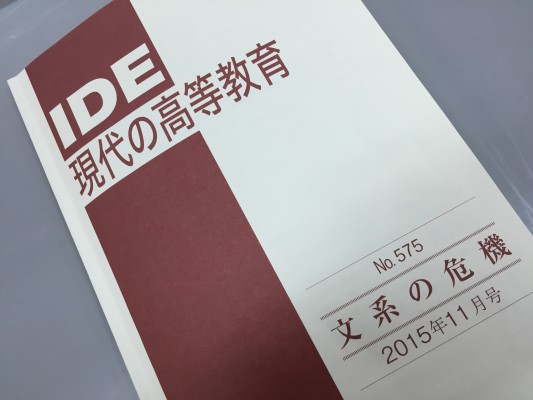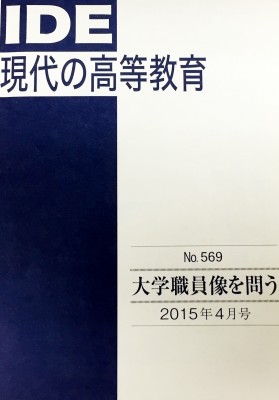離学予防について、以前読んで感心した『教学IRとエンロールメント・マネジメントの実践』のご紹介を中心に、自分の考えも織りまぜた内容をシェアします。
まずは、
- 目的
- 取り組むべき理由
- なぜ学生は離学するか?の仮説
です。
目的
- 根本的原因を断ち、離学を未然に防ぐ。
- 学生生活満足度の向上 ―離学率は学生生活満足度のバロメーター―
- 誰が、いつ、どのようなプロセスを経て、なぜ退学しているのか?をマーケティングすること
- 大学が提供している教育と、学生に必要な教育との間にあるギャップを浮き彫りにし、教育の質的向上を図る。
- 積極的離学は予防できない。予防すべきではない。消極的離学は事前に予防することが望まれる。
取り組むべき理由
(1)大学に与えるデメリット
①信用リスク
離学経験者は、高校、家庭、アルバイト先などで離学した大学のネガティブキャンペーンを張る。
②学納金の損失
1年生が1人辞めることは300万円の機会損失
③教職員のモチベーション低下
辞めていく学生を見るのは誰にとっても楽しくないもの
(2)離学後はフリーター&ニートになる確立が高い。
なぜ学生は離学するか?の仮説
- 学習面・生活面での不適応
→「学校がつまらない」「人間関係が上手くいかない」
学生生活フローからの「ズレ」が離学の原因 - 初年次教育
現在の大学教育の下地となり根幹を司るのは初年次教育。それが正常に機能していないことにいまの大学教育の問題は集中している。 - 経済的・健康上の理由
上掲書によれば、経済的理由は、インタビュー等で離学者の本音を調査した結果では少ないということです。当然それぞれの大学で事情は異なると思われます。
そのためには、仮説を導き出すための調査が必要となります。それを次回以降でご紹介します。
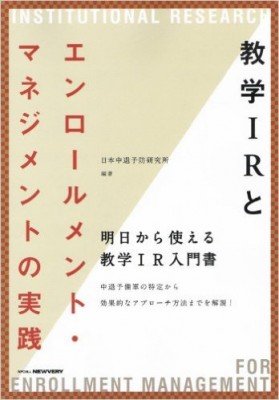
About Me
私の自己紹介はこちらです。
SNS
■Twitter:@starofuniv
■Facebook:setahiroshi
The following two tabs change content below.

大学職員ブロガーです。テーマは「大学職員のインプットとアウトプット」です。【経歴】 大学卒業後、関西にある私立大学へ奉職し、41年間勤めました。 退職後も、大学職員の自己啓発や勉強のお手伝いをし、未来に希望のもてる大学職員を増やすことができればいいなと考えています。【趣味】読書・音楽(主にジャズとクラシック)・旅 【信条】 健康第一であと10年!
最新記事 by 瀬田 博 (全て見る)
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(3) - 2018年12月25日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(2) - 2018年12月20日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(1) - 2018年12月19日