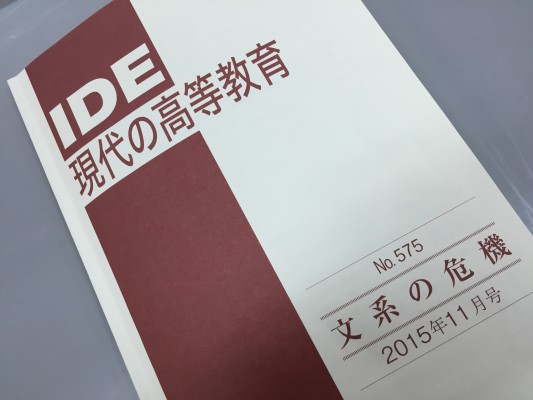「Between」誌(進研アド)の奥付ページに「読者の声」というコーナーがあります。同誌からは、発刊後に読者アンケートのメールが送られてきます。読者のフィードバックを得るという積極的な姿勢には感心しています。
最新号(2015年8-9月号通巻263号)のそのコーナーに、追手門学院大学の志村知美氏(アサーティブオフィサー)の投稿がありました。前号の特集「動き出す入試改革〜“多面的評価”の第一歩」では取材協力をされたそうです。
以下のように述べておられます。
日本の大学教育と大学入試が、本質的に大きく変わろうとしている。1990年代初めに少しだけ開いた扉から、ようやく新しい風が吹き込んできたように感じる特集であった。しかし、改革の鍵を握るのは文科省なのか。大学は経営のために入試改革を余儀なくされているのだろうか。そもそも、誰のための改革なのか。
各大学の課題に応じてどのような改革に展開しようとも、受験生の実態とかけ離れた理論、構想になってはいけない。私たちはそう肝に銘じる必要がある。これからどんな風が吹き込んでくるのか、楽しみである。
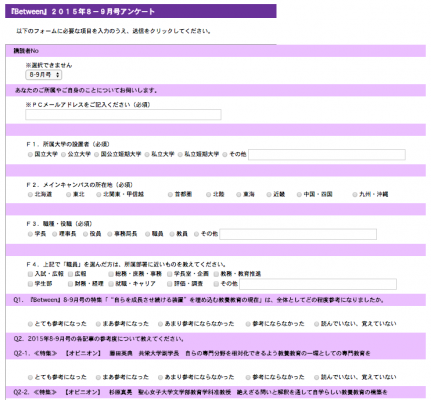
以前ご紹介した読売新聞の松本美奈氏の記事と同じように、客観的な視点による率直な意見はすばらしいと思いました。
高大接続システム改革会議「中間まとめ」(素案)によれば、新テスト等の実施は当初の予定より遅れるそうです。
個人的には、アメリカ型のアドミッション・オフィス入試が理想だと考えてきましたので、今回の高大接続改革は歓迎している立場です。それだけに(もちろん事情があってのことだと思いますが)すこし残念です。
いずれにせよ、未来の人材育成に有益なシステムこそが実現されなければならないと考えます。
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(3) - 2018年12月25日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(2) - 2018年12月20日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(1) - 2018年12月19日