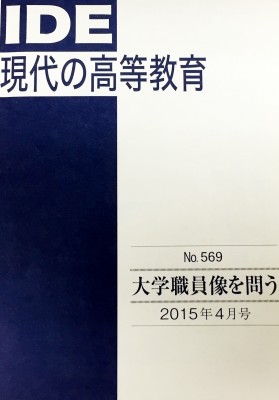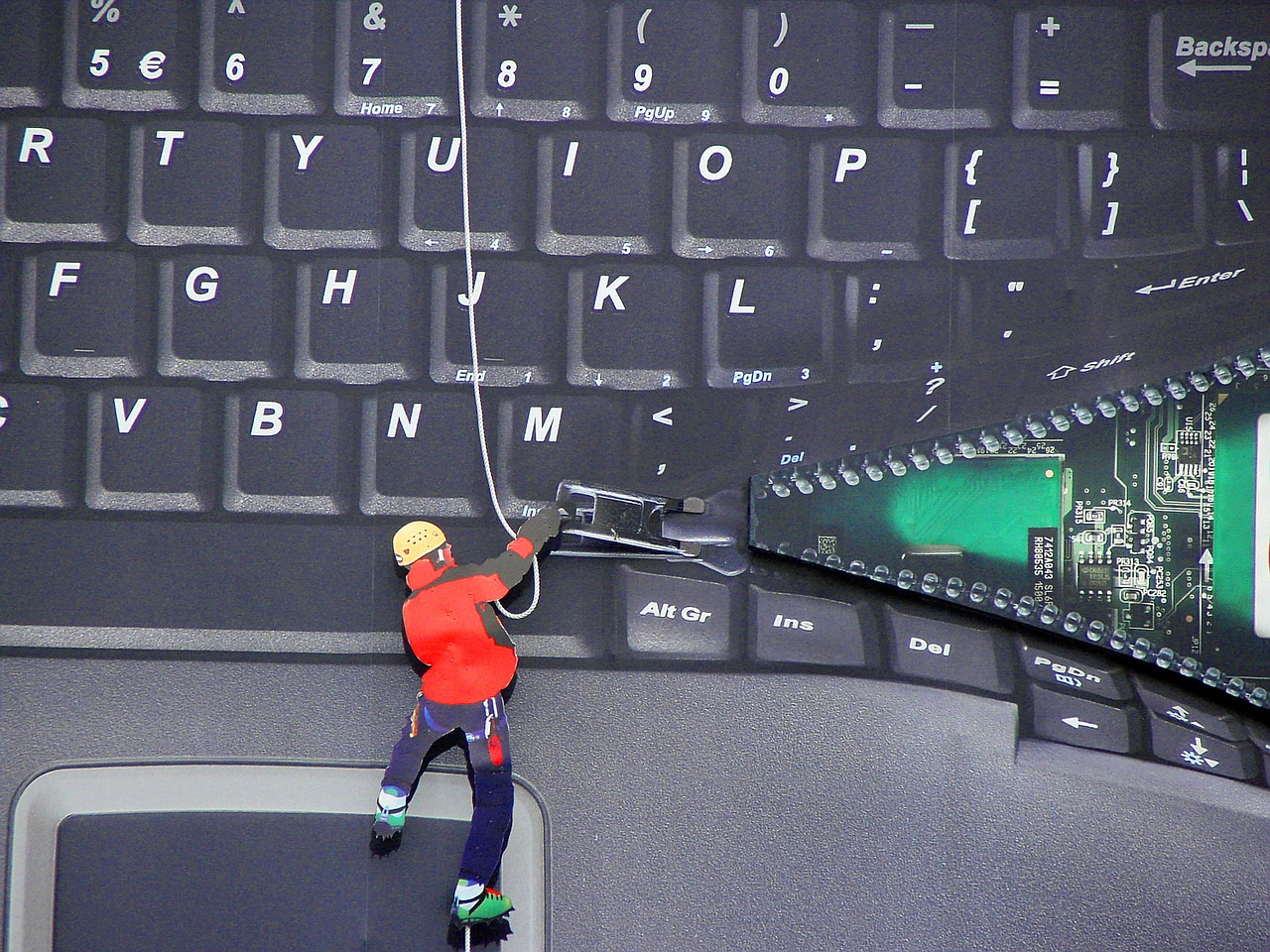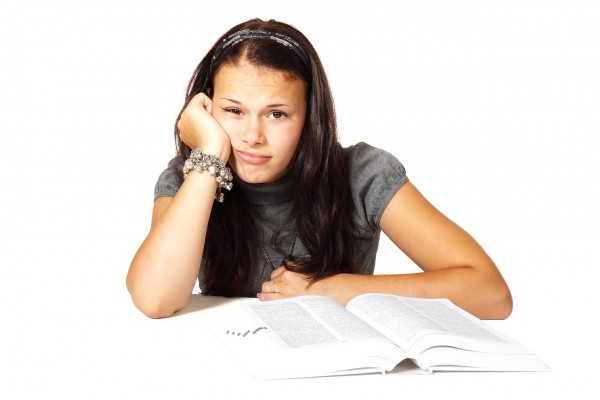届いた『IDE現代の高等教育』No.573をめくっていたところ、「取材ノートから」に目が留まりました。
著者は『大学の実力』でもおなじみの読売新聞・松本美奈氏です。非常に興味深く、かつ大学人には耳の痛い内容ですので、以下ご紹介します。
要約
どしゃぶり学会
- 朝からどしゃぶりの6月下旬の土曜日、教育関係の学会に出かけた。
- 学生の現状という時宜を得たテーマの部会で、どんな成果が飛び出すかと耳を澄ませ、懸命に聞いていても、どこがこれまでのものと違うのか、何が新しい発見と見解なのかがちっとも分からない。
- 大学院がテーマの別の部会では、さらに困惑した。5人の発表者がそれぞれに熱く語るものの、なぜ今このテーマなのか、それで何がわかったのか、さっぱりつかめない。
- 先行研究も見ていない、狙いもまとめもわからない、では実りのある議論が生まれるわけがない。これが学会なのだろうかと心底落胆した。
- 文部科学相から国立大学長らに出された通知は日本のアカデミアに欠けているものは何かを言い当てていたのか。だからこそ、学長に「そういう研究者が育つように環境整備をしてね」と頼んでいるのかもしれない。通知の姿勢を是とするつもりはない。ただ心配なのは、沈滞した学会にそれに反論し、押し戻す力を果たして期待できるのか、ということだ。
大学教育は◯◯◯◯◯だ
- 東京都内の有名大学で、大学改革の現状をテーマに話した。
- 約500人の学生に、社会は大学教育をどのように見ていると思うか、「大学教育は◯◯◯◯◯だ」の空白を埋めればどんな言葉が入るかと質問した。
- 多くの学生が「大学教育は『やくたたず』だ」とした。そのほか「意味のないもの」「テスト前に対策をしておけばこなせるもの」「就職までつなぐもの」といった答えも。否定的なものばかりで肯定的な見方はとうとう出てこなかった。
- 答えてくれた学生も、夢と希望に胸を膨らませて入学したのではないだろうか。ところが、現実は夢と希望から隔たっていた。授業はつまらない。しょせん就職活動が始まるまでのつなぎだとしたら、これまでに費やした時間と努力はどうなるのか。時の経過と共に怒りが沸き、ついにはこんなものだと諦めの境地に達する・・・。
- 一方で、ひとりひとりの学生の心に火をつけるべく奮闘している教員たちがいるのも事実
- 「いまの大学教育」とひとくくりにするには、現実は多様
大学はかっこよくなるところ
5歳の息子さんが通う保育園で、松本氏は同じクラスの女の子から唐突な質問を受けます。
「ねえ、大学って何するところ?」
何と答えたものかと頭をひねっているうちに、その彼女は、
「わかった。かっこよくなるところだよね」
と自分で回答を用意してみせたとのことです。
感想
「大学教育は『とても有益』だ」
「大学教育は『勉強ばかりで大変』だ」
「大学教育は『自分が成長できるところ』だ」
社会は大学をこんなふうには見ていないと学生が思っているわけです。ほかならぬ大学自身の宣伝コピーではよくお目にかかりますが・・・。大学にとってこれほど残念なことはありません。
一国の高等教育理論をリードしなければならないはずの学会が、先行研究も見ていない、狙いもまとめもわからないという体たらくではお先真っ暗ではないでしょうか。
救いは、奮闘している教員がいるということです。もっともっとこんな教職員が増えるといいですね。
「かっこよくなるところ」になるためにはどれだけの月日が必要なのでしょうか。大学人としては、いささか心配です。
The following two tabs change content below.

大学職員ブロガーです。テーマは「大学職員のインプットとアウトプット」です。【経歴】 大学卒業後、関西にある私立大学へ奉職し、41年間勤めました。 退職後も、大学職員の自己啓発や勉強のお手伝いをし、未来に希望のもてる大学職員を増やすことができればいいなと考えています。【趣味】読書・音楽(主にジャズとクラシック)・旅 【信条】 健康第一であと10年!
最新記事 by 瀬田 博 (全て見る)
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(3) - 2018年12月25日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(2) - 2018年12月20日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(1) - 2018年12月19日