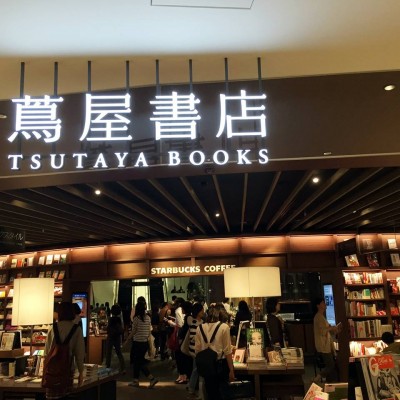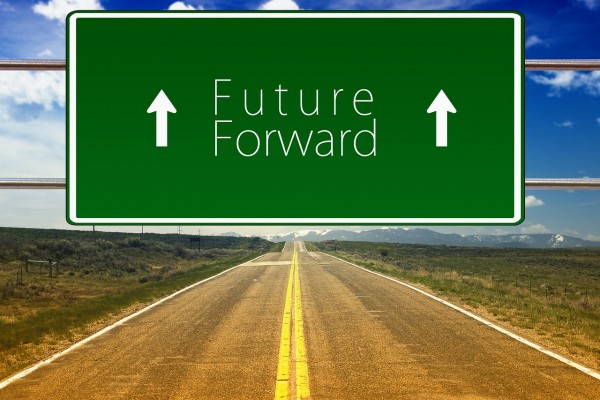「『事務』職員から『大学』職員へ」第5回目です。
この記事は、福島一政氏の第1回高等教育推進センターSD講演会(関西学院大学)での講演をご紹介するものです。
出典:関西学院大学高等教育研究第2号(2012年3月)
今回は、「大学改革が進まない理由―偏差値志向ー」です。
偏差値によらない大学選び
大学改革が進まない理由として、まず偏差値信仰が挙げられています。
福島氏は、
- 最近は偏差値によらない大学選びという流れに変わりつつある。
- ちゃんとした大学を作る、それぞれの特色を活かした大学づくりをしていくと結果が出る。
と述べています。
偏差値の弊害
大前研一氏は次のように述べています。
「偏差値導入を主導した政治家の口から直接、『(安保闘争に懲りて)国やアメリカに逆らわない従順な国民をつくるために偏差値を導入した』と聞いたことがある。
政府の狙い通り、偏差値教育によって“身の程”をわきまえた従順な日本人は増殖した。
しかし、同時に日本の近代化、戦後復興、高度成長の原動力にもなった日本人のアンビション、気概、チャレンジ精神をすっかり削いでしまったと思う」
(「文科省提言『G大学・L大学』は、若者をつぶす」大前研一の日本のカラクリ)
評価されるべき大学とは
入口ではなく、「教育力」で評価される大学が増えることを願いますし、またそうならねばならないと思います。
選抜制の有無にかかわらず、それぞれの大学の特色を活かした大学づくりをしている大学が評価されるべきです。
これまでの大学はあまりにも教育が疎かにされすぎていたことは多くの指摘があるとおりだと思います。
⇒第6回:大学改革が進まない理由―大学経営のプロが決定的に不足している― 「事務」職員から「大学」職員へ(6)を読む。
【目次】「事務」職員から「大学」職員へ 福島一政氏の講演から
The following two tabs change content below.

大学職員ブロガーです。テーマは「大学職員のインプットとアウトプット」です。【経歴】 大学卒業後、関西にある私立大学へ奉職し、41年間勤めました。 退職後も、大学職員の自己啓発や勉強のお手伝いをし、未来に希望のもてる大学職員を増やすことができればいいなと考えています。【趣味】読書・音楽(主にジャズとクラシック)・旅 【信条】 健康第一であと10年!
最新記事 by 瀬田 博 (全て見る)
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(3) - 2018年12月25日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(2) - 2018年12月20日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(1) - 2018年12月19日