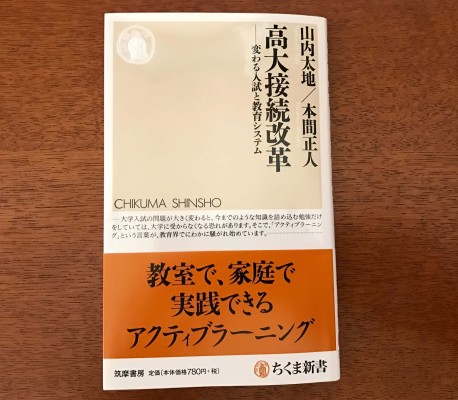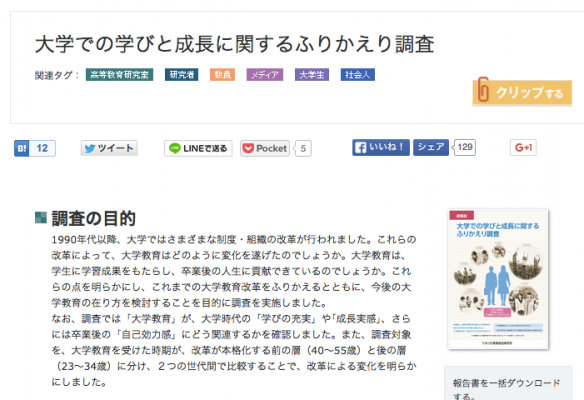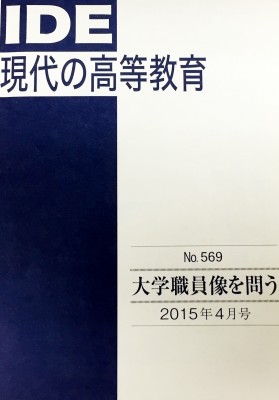このページの目次
はじめに
売れているようである。
教育ジャーナリストで(社)大学イノベーション研究所所長の山内太地氏と京都造形芸術大学副学長・教授の本間正人氏の共著である。
この1冊で、
- 高大接続改革入試の概要
- 受験生・保護者が心がけるべきこと
- アクティブラーニングの定義
- 高校・大学での先進的な取り組み
について知ることができる。
さっそくご紹介しよう。
高大接続改革ー変わる入試と教育システム
目次
目次は以下のとおりとなっている。
【注】( )内は執筆者
はじめに(山内氏)
第1章 2020年の大学入試(山内氏・本間氏)
第2章 偏差値で人生が決まる―身も蓋もない学歴論(山内氏・本間氏)
第3章 本間先生に聞きたい、アクティブラーニングのQ&A(本間氏・山内氏)
第4章 高校生までにできること(山内氏)
第5章 大学のアクティブラーニング事情(山内氏)
あとがき(本間氏)
知識伝達型の授業の時代が終わり、学習者中心の学びへ
「はじめに」では、本書の内容が簡潔に述べられている。
高校・大学の現場では、どんな「アクティブラーニング=能動的な学習」を生徒・学生にさせたらよいのかという議論が盛り上がっている。
偏差値は学力による人材の選別として有効であり、有名大学を目指すのは正しい。
高校、親、受験業界、マスコミのニーズを無視して、大学周辺だけで「偏差値より中身」と教育の理想をいくら語っても、市場に見放されて定員割れし、経営が悪化している4割の私立大学が救われるわけでもない。
2020年の大学入試ーセンター試験が2つに分かれたもの
大学入試センター試験に替わって実施予定の、「高等学校基礎学力テスト(仮称)」と「大学入学希望者学力評価テスト(仮称)」について述べられている。
「高校テスト」と「大学テスト」。一般人の感覚としては、センター試験が2つに分かれたと考えておいて問題ない。
いいかえれば「高校で学力が身に付いたかどうかを見る試験」と「大学で学ぶ能力があるかどうかの試験」ということになる。
入試は多様化するものの、主流は、今までどおりの、学力を重視する(ただし、建前としては「学力の3要素」に従った高校教育や大学の入試形態になる)入試は、極端には変わらない。
教育上で重要なのは、2020年のセンター試験廃止ではなく、2022年の高校の学習指導要領の改訂、という指摘は、大学人としては、注視すべきことだと感じた。
高大接続が大学教育を改善するかは疑問ー大きく変わらないのは雇用の問題
高大接続が大学教育を改善するのか?
このことについて、雇用の仕組みが変わらないかぎり、それは疑問だと著者は述べている。
終身雇用・年功序列の企業は、大学教育の中身ではなく、大学名のブランド、偏差値などを重視し、大学の専門性や、大学に入ってからどう本人が学び、成長したのかは、大きくは問わない。
高校教育、大学受験、大学教育を改革しても、その先の就職の仕組みが変わらない。
新卒一括採用廃止の可能性が出てきた昨今だが、今後のことはまだ不透明である。
大企業をはじめとする雇用の仕組みが変われば、大学教育も変わるのか。
このことについての真摯な検討が望まれる。
高校・大学が取り組むべきこと
挙げられている項目のうち、2・3点ご紹介しておく。
詳細は本文をお読みいただきたい。
- 志望する高校で、どのようなアクティブラーニングが行われているのかも、重要な学校選びの基準に。
- 従来の暗記型の大学受験に特化した教育をする進学校は、変化しなければ生き残れない。
- 大学には「個々の学生の主体性をさらに引き出す多様な学びの場をつくり、十分な能動的学修とそれを支える広く深い知識・技能を獲得できるようにする必要がある」ことが求められる。
偏差値で人生が決まる?身も蓋もない学歴論
「賢人と愚人との別は、学ぶと学ばざるとに由って出来(いでく)るものなり」(福沢諭吉)が引用されている。
偏差値の高低によって、就職先にどのような違いがあるのかということについて述べられている。
- 有名な大学、偏差値が高い大学の場合、公務員、そして金融、製造業などの優良企業に行く傾向が強い。
- 大学の偏差値が下がると、公務員、製造業、金融の割合が徐々に下がり、卸売・サービスが増加する。
- 私たち日本人のメンタルは、優秀な人ほど、「良い高校から良い大学に入れば、安定した公務員や大企業に行ける」というもの。
これが、わが国の現状であることは間違いないであろう。
教師の役割はアクティブ・ラーナーとしてのお手本になること
教師の役割として最も重要なのは、うまく授業をこなすことではなく、「アクティブ・ラーナーとしてのお手本になる」ことだという。
知識なしにアクティブラーニング型の授業をすることに疑問を持っている、とも指摘されている。
これには全面的に賛成である。
知識はすべての学習の基本である。それなしに授業スタイルだけを変えるだけで効果があるのかは、いささか疑問である。
そして、教員だけではなく、高校・大学の構成員全員が、そして保護者も、自身がお手本になるべきなのだろう。
高等学校での先進的な取り組み
3校が紹介されている。
- 近畿大学附属高等学校・中学校(iPad教育)
- 岐阜県立可児高等学校(課題解決型キャリア教育の地域移管と全体参加)
- 愛知県私立桜丘高校(「自ら学ぶ進んで学習する習慣が身に付く」ことに力を入れている)
岐阜県立可児高等学校教諭のつぎの談話が紹介されているのが印象に残った。
いちど故郷を離れ、大学などで高い専門性を身に付け、感覚を磨き、人脈をつくる。そのうえで地元に帰郷して起業・創業するのが、これからの地方の普通科高校のあり方。
すばらしい考え方である。
ぜひそうなってほしいと願っている。
大学のアクティブラーニング事情
大学の取り組みとして、以下の4大学が紹介されている。
- 早稲田大学(「全学共通副専攻」など)
- 西南学院大学法学部(SA=スチューデント・アシスタント)
- 金沢工業大学(新しいアクティブラーニング)
- 愛知淑徳大学(初年次教育など)
早稲田大学の項では、“ぼっち事情”についても多くの字数が割かれており、興味深い。
最後に山内氏は、今回の教育改革が、多くの受動的な、他人からの評価で生きる日本人のメンタルを変えていけるのなら、前向きに評価したい、と述べておられる。
まとめ
自ら学ぼうとする気概をもった生徒・学生が多く出てほしい。
これが本書を読んだ感想である。
たとえ不十分な教育システムであっても、大いに学校を使い倒してほしい。
そういった生徒・学生には教員も諸手を挙げて歓迎してくれるだろう。
本間正人先生も、つぎのように述べておられる。
一生涯を通じて学び続け、社会の変化に対応し、自らの特質を発揮できる人材になっていくことが求められる。
これこそが、アクティブラーニングの到達点ではないだろうか。
山内氏には、今後もこのような良書を刊行していただきたい。
行動することでしか得られない、大学と高校についての知見は、同氏にしか書けないことだからである。
あまり収益にはつながらない仕事かもしれないが(失礼)、出版は大事な啓蒙活動である。
引き続き精力的に活動していただきたいと願っている。
蛇足を付け加えれば、本書は大学人には必読である。

- 作者:本間 正人,山内 太地
- 出版社:筑摩書房
- 発売日: 2016-10-07
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(3) - 2018年12月25日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(2) - 2018年12月20日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(1) - 2018年12月19日