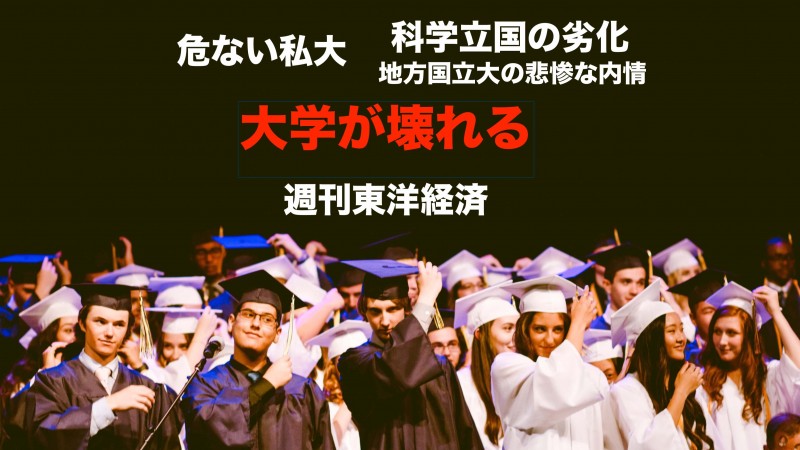このページの目次
はじめに
『大学マネジメント』(NHK出版)所収、舘昭氏による「11章 評価と大学マネジメント」からのご紹介。
同章の中心テーマとして述べられている認証評価については、次回ご紹介する。
ここでは、
- なぜ大学が国家行政組織と教授団だけでは運営できないのか?
- なぜ大学改革はうまく行かないのか?
という、大学職員の多くが疑問を持っているであろう2つの問題についての回答が、著者の舘氏から提示されている。
筆者なりにまとめた内容を、以下ご紹介しよう。
大学の機能に則した組織的マネジメントの確立
要請される大学マネジメントの確立
評価制度の改革も、知識基盤社会下における研究と教育の機関という、現代大学の機能に則した組織的マネジメントの確立の下での評価の展開が必要となっている。
これまでの大学の運営は、学者たちによる経験的なものであった。
しかし、今日では、大学におけるマネジメントの確立が要請されている。
日本の大学のそれへの適応は外形的なものにとどまり、内実では大きな問題を抱えている。
大学を研究と教育の持続的な展開の場としたのは、19世紀のベルリン大学を嚆矢とするドイツ大学であった。
それを支えたのが国家官僚の外的な統制の下での学者集団(教授団)の自治という運営形態であった。
このモデルは、今日のように研究が社会に直接の効果を及ぼすまで発展した。
しかし、社会と学問の関係が複雑化、緊密化すると、形式的な統制手段しか持たない国家行政組織と学問に埋没した教授団とだけでは機能できなくなる。
あるべき大学のマネジメント
この要請に応える組織構造を、すでに持っていたのはアメリカの大学である。
国家は外的な環境として存在するにとどまり、大学内では一般社会人の理事会によるガバナンス、その雇用する学長(プレジデント)、その任命する学監・学部等(プロポスト、ディーン)によるリーダーシップという上からの流れと、学問分野ごとに学科(デパートメント)に結集する、テニュアード教員を核とするコミュニティという下からの流れがぶつかり合うなかで、そこに専門性のあるマネジメントが発生していた。
この組織構造の下では、発生する視野の狭窄は、強力なリーダーシップの下で払拭することができる。
弾力化しつつある社会からの無方向の圧力は、マネジメントによって、学問の内在的発展へと方向付けることが可能なのである。
ヨーロッパでは、国家行政機構による統制はアカウンタブル・オートノミー(説明責任を負った自律)の標語の下で統制から評価へと変化し、大学は厳しい評価にさらされつつも本格的な自律経営が可能になり、学者層からマネージャーが生まれている。
大学が、内から沸き起こる研究と教育の核を持たない限り
日本の大学で現在進められている改革は、このままでは、とても研究と教育の持続的展開の保証する、大学マネジメントの形成とまでは至りそうにない。
時代が日本の大学に提示しているのは、学問と社会の関係の複雑化、緊密化に応えるという世界的課題である。
この過程のなかで、大学が、内から沸き起こる研究と教育の核を持たない限り、社会は無理解に大学の内部構造に介入してくる。
アメリカの大学ではもともと低く、ヨーロッパでは後退を見せている政府の介入を、日本では強める結果となっている。
大学改革の象徴とされる講座制の廃止、教員の任期制、教員の評定、大学評価、競争的資金配分のどれをとっても、社会からの強い圧力の下に、政府の介入によって実施に移されている。
それは、一見、自律的な研究・教育の展開を促す施策のように見えるが、実態は、形式的な作業に終わっている。
そこには、マネジメントの発生が見られない。
学長にリーダーシップの名の下に独裁的な権力を与えたところで、マネジメントが成立するわけではない。
大学のような公共機関においてマネジメントが成立するためには、まずガバナンスが存在しなければならない。
まとめ
ではどうすればいいか?
舘氏は以下のように述べておられる。
必要なのは、講座制の解体によって教員がばらばらの個人になることではなくて、自律的な学問の担い手としてディシプリンごとにコリーグとしてデパートメントに結集することである。
そして、その担い手としての資格を証明するものとして、テニュアトラックにおける任期制の下で評価にさらされた試錬の期間がある。
率直に言って、筆者はこの文章をよく理解できなかった。
ただ、自律的な研究・教育の展開を行わねばならないということが重要だと受け止めた。
このことは、教員(教授会)のみならず、経営層・職員も含めた大学全体の課題ではないだろうか。
さて、「まえがき」で述べた2点についての回答は、以下のようになるだろうか。
- なぜ大学が国家行政組織と教授団だけでは運営できないのか?
社会と学問の関係が複雑化、緊密化すると、形式的な統制手段しか持たない国家行政組織と学問に埋没した教授団とだけでは機能できなくなる。
知識基盤社会下における研究と教育の機関という、現代大学の機能に則した組織的マネジメントの確立が必要になったから。
- なぜ大学改革はうまく行かないのか?
内から沸き起こる研究と教育の核を持っていないから。
米国・ヨーロッパでは、すでにあたらしい時代に適応したマネジメントが行われているようだ。
もちろん日本には日本のやり方があるだろう。模倣や追随がよいわけではない。
だが、「学問と社会の関係の複雑化、緊密化に応える」という世界的課題に応えることなく、形式的な大学改革が行われている実情があるとすれば、そうも言っていられないのではないか。
あたらしい時代に合わせたガバナンス(とマネジメント)を構築し、そして、構成員全員で大学を運営していく。
このことの重要性を強く感じさせてくれる論考である。

- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(3) - 2018年12月25日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(2) - 2018年12月20日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(1) - 2018年12月19日