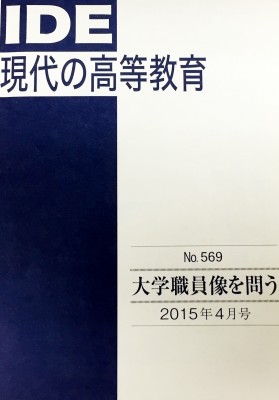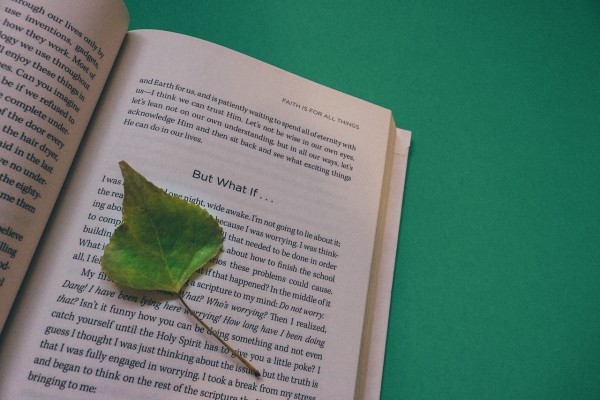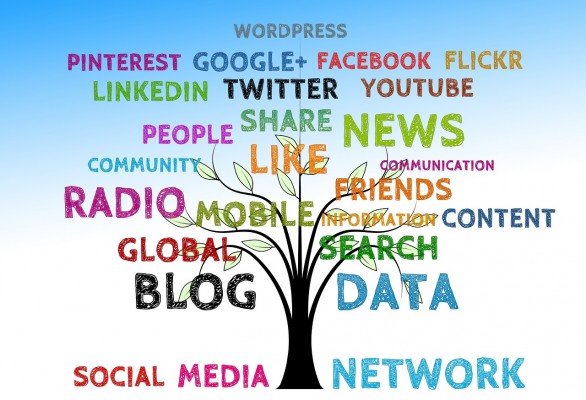大学行政管理学会の2016年度定期総会・研究集会が、2016年9月9日(金)〜11日(日)に開催される。
その研究・事例研究発表のプログラム一覧を読んでいたら、ちょっと面白そうなテーマを見つけた。
利(きき)大学
京都文教大学教務課の皆さんが実施されている「複数大学連続訪問型SD研修手法『利(きき)大学』についての考察」。
概略を読むと、こうある。
- 「利(きき)酒ならぬ利(きき)大学(以下、利大学)と称する SD 研修手法
- 利大学の目的は、
①自己相対化促進
②主体性促進
③モチベーション増進
④チームビルディング促進
の四つである。
- 本研修の特徴は、
①所属職員全員(原則)が
②複数の他大学同部署を
③学生がいる平日に
④1日のうちに一気に回り
⑤組織風土や職員の考え方に触れる
という手法にある。
- 特に、「1日のうちに一気に回る」ことが最大の特徴であり、自己相対化促進に強く焦点を当てている。
- 複数の他大学同部署の組織風土を一気に「味わう」ことで、強み・弱み発見力が促進される。
- また、次々に大学を巡るにつれ、「これは面白い、やってみたい」という主体性が生じ、実際に「やってみよう」というモチベーションが生じる。
- さらには、他大学同部署との比較経験を共有する中で、集団凝集性が高まり、チームビルディング効果が生じる。
まとめ
「所属職員全員(原則)が、学生がいる平日に」他大学を訪問するということは、本務校のオフィスが空(カラ)にならないか人ごとながら心配になる。
もう一点。他大学を訪問することの是非について。
競争相手である他大学を訪問するということは、ほかの業界では考えられないことだとよく言われる。
しかし、大学は非営利組織で、公的なものであるのだから、あながちおかしなことではないのかもしれない。
いまやあらゆる情報がネットに溢れている。大学情報も例外ではない。
コンフィデンシャルな情報を得ることそれ自体がアドバンテージになる時代は終わった。
たとえ「こうすれば成功できる。生き残れる」という解答を得たとしても、それを実行する(できる)者はごく僅かなのだ。
筆者はそう考えている。
ともあれ、当初は違和感を持ったこの研修だが、前向きで行動的な意欲に敬意を表したい気持ちになった。
陰ながら応援したい。
The following two tabs change content below.

大学職員ブロガーです。テーマは「大学職員のインプットとアウトプット」です。【経歴】 大学卒業後、関西にある私立大学へ奉職し、41年間勤めました。 退職後も、大学職員の自己啓発や勉強のお手伝いをし、未来に希望のもてる大学職員を増やすことができればいいなと考えています。【趣味】読書・音楽(主にジャズとクラシック)・旅 【信条】 健康第一であと10年!
最新記事 by 瀬田 博 (全て見る)
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(3) - 2018年12月25日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(2) - 2018年12月20日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(1) - 2018年12月19日