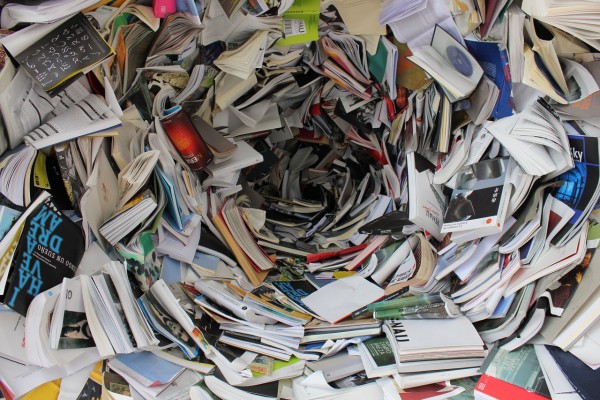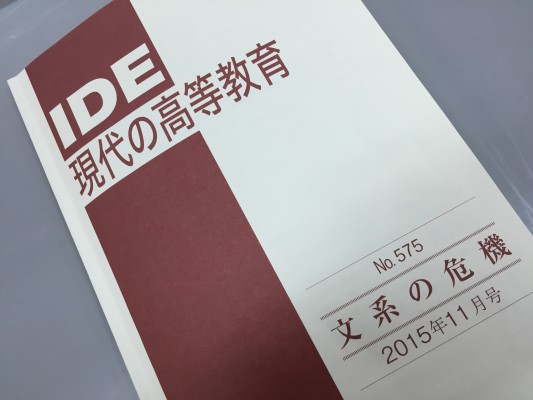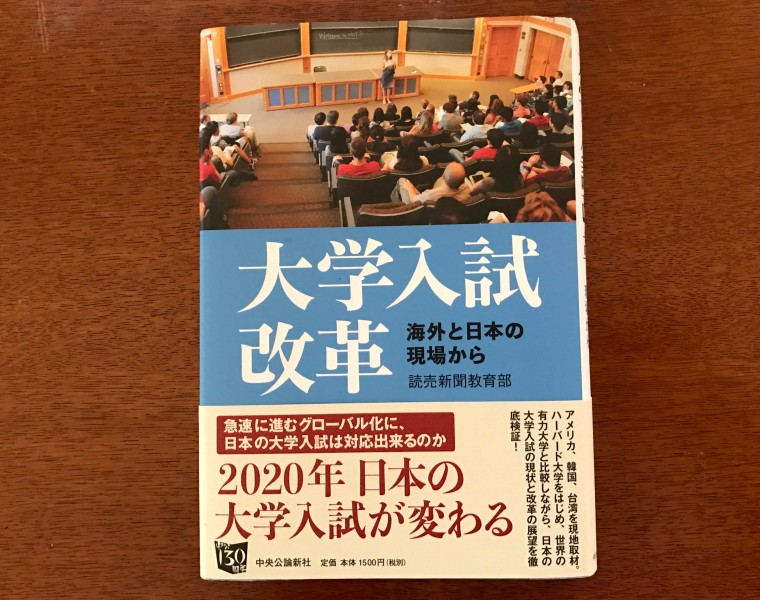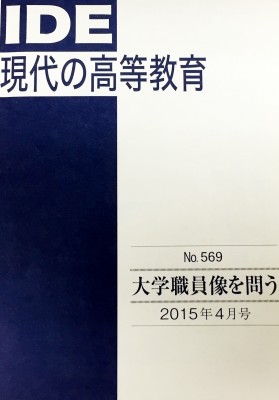「IRの基本原理と米国での活用、日本での応用」
【講演】山田礼子氏(同志社大学社会学部教授)
前回に引き続き、私学高等教育研究所シリーズ(研究報告)No45(IRの基本原理と活用―国際比較と日本型IR)から、山田礼子氏の講演のご紹介である。
ともすれば、評価指標の選定やデータの一元化といった話題が先行しがちなIRだが、その前段階として考えるべきことがある。
そのことについては、前回でご紹介した。
今回は人材養成編である。
それではご紹介しよう。
「インスティテューショナル・リサーチャーとアイアーラー」ー研究志向ではない機関のためのアイアーラーの育成を
IR部門を大学の中で位置づけていくときに、基本的に以下のことは意識しなければならないところ。
【考えるべきこと】
- アイアーラーなのか、インスティテューショナル・リサーチャーなのか。
- データ係か、戦略立案者か、研究者なのか。
- 専門職か、研究者か、一般職員なのか。
- 外向け部門か、内部部門か、研究部門なのか。
山田氏の考え
- アイアーラーなのか、インスティテューショナル・リサーチャーなのか。
→(山田氏)中間だと考える。研究者的側面もあるし、アイアーラーとして徹底的に機能していく、その中間に位置づけられる。 - データ係か、戦略立案者か、研究者なのか。
→(山田氏)研究者そのものではなくて、データ係と戦略立案者の中間に位置する存在ではないか。 - 外向け部門か、内部部門か、研究部門なのか。
→(山田氏)執行部にとって意思決定をするための支援機関であるから、内部部門である。 - 研究優先だとIRはなかなか日本の大学ではうまく機能しない。
人材の育成
- 一般的な知識技能・分析能力、大学の部局、特殊用語に関する知識、調査、基本的統計技術、基本的データベースの知識というところがいわゆる採用・研修段階で、エントリーレベルでのIRを担当する人たちに求められるもの。
- 研究志向でなくて、機関のためのアイアーラーになることを理解した人材を養成していかなければIRは広がらないと思うし、そうしたことを意識して、これからIRを設置していこうと考えておられる大学は、ぜひそうした人材を養成していくことにもご関心を持っていただければと思う。
Forward←【(1)組織編】へ
The following two tabs change content below.

大学職員ブロガーです。テーマは「大学職員のインプットとアウトプット」です。【経歴】 大学卒業後、関西にある私立大学へ奉職し、41年間勤めました。 退職後も、大学職員の自己啓発や勉強のお手伝いをし、未来に希望のもてる大学職員を増やすことができればいいなと考えています。【趣味】読書・音楽(主にジャズとクラシック)・旅 【信条】 健康第一であと10年!
最新記事 by 瀬田 博 (全て見る)
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(3) - 2018年12月25日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(2) - 2018年12月20日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(1) - 2018年12月19日