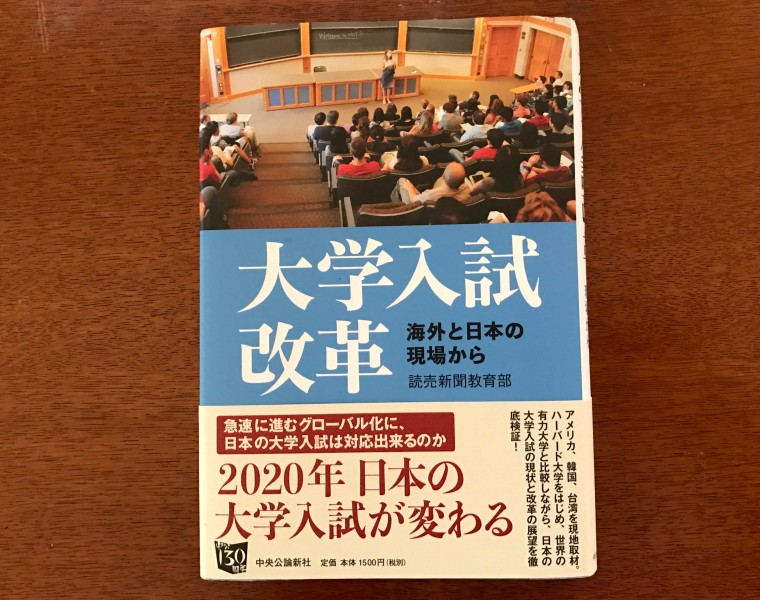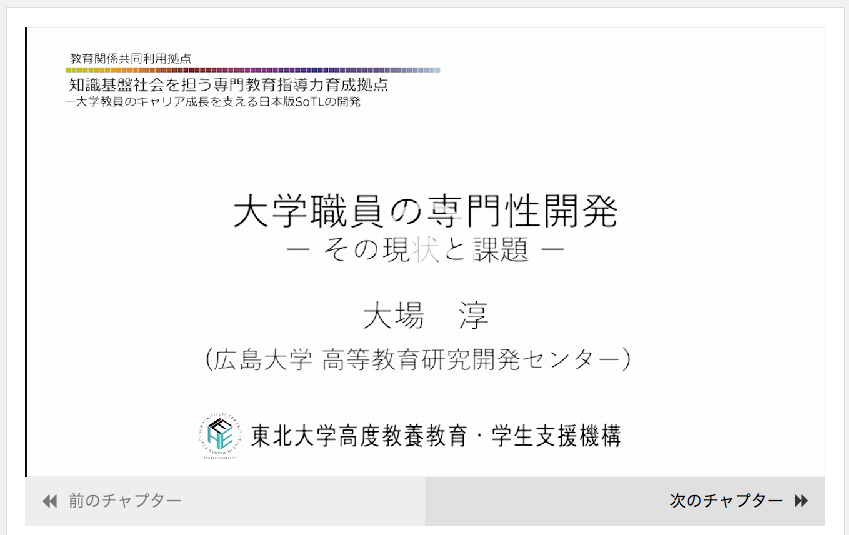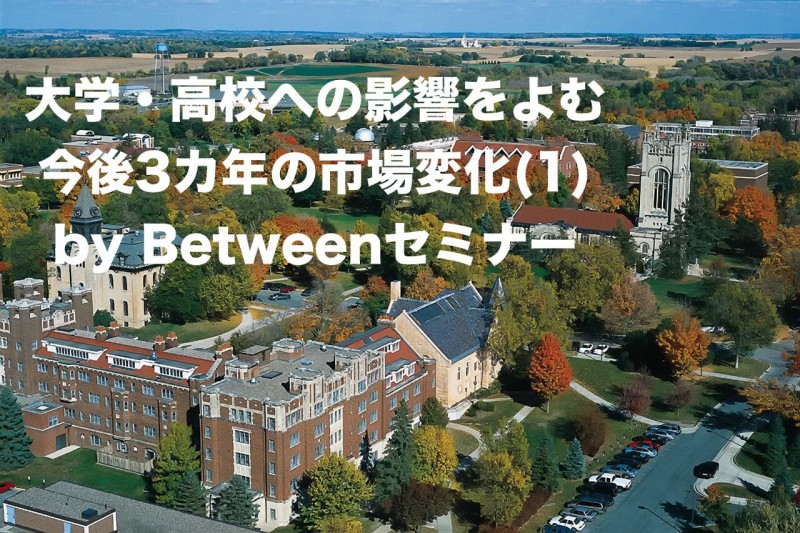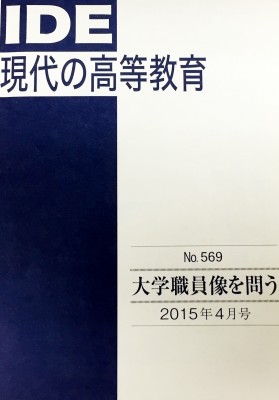このページの目次
はじめに
国立台湾大学では、入学者の41%がAO型入試で、韓国では、大学の総募集枠に占めるAO型入試が66%。
こういった現状を、読者の皆さまはご存知であろうか。
両国とも全国一斉試験の厳しさだけが喧伝されているが、アメリカ型入試を参考に、上記のような改革がすでに進んでいることを、本書は教えてくれる。
トップを走る米国、大胆な新興国の入試改革と、「変われない」日本の現状を比べても、なお一点刻みの選抜を続けている場合だと思いますか?
「日本的な試験風土」。それこそが、いま変えなければと論議されているもの。
このような問題意識がつらぬかれた、精力的な取材にもとづいた労作である。
大学入試改革 海外と日本の現場から
目次は、以下のとおりとなっている。
第一章 世界が注目 米国の潮流
第二章 多面的な入試 アジアでも
第三章 二〇二〇年、日本の大学入試が変わる
第四章 改革は現場から
第一章では
- SAT、ACT
- ウィリアムズ大学
- ブラウン大学
- 高校での「AP(大学進学準備)プログラム」
- ハイスクール
- 福井大学
- 国際教養大学の暫定入学制度
などについて述べられている。
米国の大学では、入学後の貢献度を重視している。
第二章では、
台湾と韓国の現状、各国の入試制度について述べられている。
個人的には、本書でもっとも充実した内容だと感じた。
台湾
- 共通テストを年2回実施。
- 指定科目考試、AO入試、繁星推薦入試
大学側の改革に対する姿勢が強く、発言力の強い大学が、ほかの大学にも影響を与えてきた。
韓国
- AO型入試「随時募集」
- 専従の「入学査定官」
- 過度の受験戦争を抑えるのが目的
大学に対する政府の権限の大きさは日本の比ではない。
第三章では、
新入試についての現状についてのレポートである。
第四章では、
- 東大・京大・阪大のAO・推薦入試
- 東北大学
- 九州大学の「二一世紀プログラム」
- 早稲田大学
- 佐賀大学
- お茶の水女子大学
- ICU(国際基督教大学)
- 聖学院大学
各大学の取り組みについて述べられている。
先を行く医学部入試についてのレポートが興味深い。
何のための入試かをいま一度考え直す
大学入試センター試験の場合、「1点」が重すぎることが厳格な運営につながっているという指摘があり、最終的には1点差が合否を分ける。
SATなどの海外の共通テストでは、それはまずない。
「多面的・総合的な評価による選抜」を進めていけば、過剰ともいえる労力を注ぐ必要がなくなる。
以上の指摘は、「多面的・総合的な評価による選抜」方式の、意外なメリットではないだろうか。
予習・復習をする前提でカリキュラムが組まれていない日本の大学
第一章で紹介されている米国のブラウン大学。
福井大学は同大学の教育センター長を招聘し、授業やカリキュラムなどを視察してもらった。
その結果が、以下のとおり紹介されている。
- 授業の予習・復習をする前提でカリキュラムが組まれていないのでは。
こんなに過密なカリキュラムでは、学生はいつ予習や復習をするのか。米国では考えられない。
- 大学側が入学後の学生が学習に励むよう「働きかける」ことの重要性。
大学には、学生の学習意欲を喚起する責任がある。
優秀な学生でも、放っておいては自動的に必死で勉強するようにはならない。
- 日本では大学に入るのが難しく、入試がゴールになってしまっている。
私たちの大学では、学生たちは大学で得られるものをすべて吸収しようと必死に勉強している。
これでは、大学そのものを作り変えないといけないとさえ感じる指摘で、暗澹たる気持ちになる。
とりわけ、過密なカリキュラムの問題は深刻である。
授業外学習の少ないことが、わが国の大学最大の課題であるからである。
単位数を減らすだけではなく、就職活動で事実上学生生活が3年となっていること、3年間でほとんどの単位が取得できること、など課題は多い。
入学後の貢献度を重視する
「その学生が入学することで何か大学にもたらされるものがなければ、大学としては必要ない」(スタンフォード大学)。
最低限の学力は必要だが、多様な活動への貢献度を重視するというわけだ。
「入学後の貢献度を重視するという発想は日本の大学にはほとんどない」と指摘されている。
定員充足に四苦八苦でそれどころではない中小大学だけではない。大手ブランド大学でもこのような方針で選抜を行っているところは少ないにちがいない。
アドミッション・オフィサーの育成・配置が必須
本書では、米国、韓国の例が報告されているが、多面的・総合的な評価による入学試験制度には、担当者の育成と配置が欠かせない。
とりわけ、韓国の入学査定官が参考になるのではないか。
「入学査定官」とは、アドミッション・オフィス(入学事務室)に配置された専門職員で、現在約630名。4年制大学の8割にあたる166校が導入している。
加えて国からの財政補助も必要である。
まとめ
数年度にはあたらしい入試制度がスタートする。
本書で指摘されている項目は、
- 多面的・総合的な評価による選抜(入学後の貢献度を重視)
- アクティブラーニングによる双方向的な授業
- 時代に適合した教育コンテンツの提供
- 授業の予習・復習をする前提で編成されたカリキュラム
などである。
これらが実現したとき、日本の大学は、見違えるように変わるのかもしれない。
ぜひご一読いただきたい。

- 作者:読売新聞教育部
- 出版社:中央公論新社
- 発売日: 2016-07-06
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(3) - 2018年12月25日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(2) - 2018年12月20日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(1) - 2018年12月19日