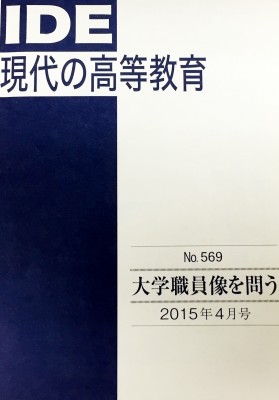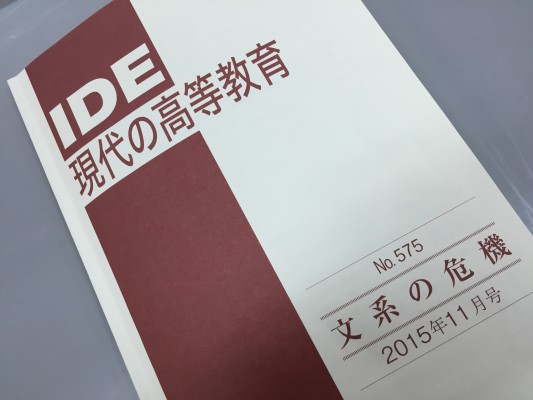副題が「親子で考える『失敗しない大学の選び方』」となっているこの対談ですが、面白かったのでご紹介します。
「カレッジマネジメント」の進学ブランド力調査2015をもとに、失敗しない今どきの大学の選び方を考えるというテーマです。
このページの目次
要約
明治大学はなぜ人気があるのか
- 「“あこがれ校”よりも“チャレンジ校”を目指したい」という高校生。“チャレンジ校”とは「頑張れば行ける有名大学」という位置づけの大学のことで、明治大学はこのポジションを確立。“あこがれ校”は早慶。
(調査で)上位にランクインする大学は大学改革に積極的
- 明治大学は、学部・学科も多様になり、女子学生を増やすためにキャンパス環境への投資も惜しまなかった。
- リバティタワーは明治大学の改革の歴史の象徴
- 卒業生のイメージも昔はバンカラだったが、今は高校生のあこがれの卒業生がいる。
- 中長期のブランド作りがポイント。明治大学ならではの世界観を、諸々の努力と、時間をかけて構築している。
- 関西・東海は国公立志向が高い。これは景況感の地域差。
大学と学部がわかりずらい時代、何を学べるのか
- なぜ大学のイメージが伝わりづらくなってしまったか。
①進学率が上昇し、大学が増えたこと
競争相手が増えることによって、大学の発信力も相対的に弱まっている。
②学部・学科の増加
ひと目見ただけでは、何を学べるかわからない学部名・学科名が増えた。1991年の学部は29種類、それ以降約700種類まで増加している。
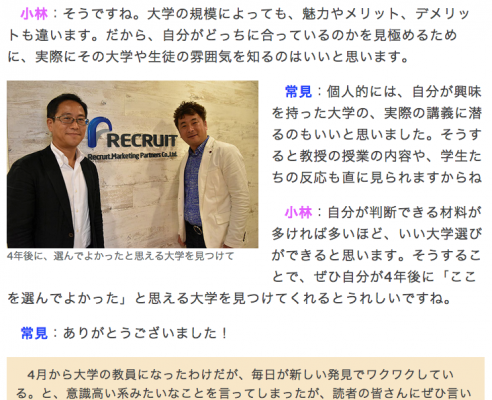
偏差値だけで大学を選んではいけない
- すでに高校生が「偏差値なんて信用できない」と考えている。
- 入るときの偏差値ではなく、入った後に自分がどうなっているかを意識したほうが、いい大学選びができる。
- 親が大学を選ぶときに意識する項目は「入試情報」から「授業料」「就職実績」にシフトした。
- 常日頃、自分の子どもが何になりたいか、どんな大人を目指しているのか情報共有しておくといい。
- 「国際関係・国際文化」「医療・保険・衛生」の分野は伸びている。
オープンキャンパスに出かけて大学を見に行こう
- 正解が見えない不安定な時代だからこそ、他人から与えられるのではなく、自分に合った大学を探してほしい。
- オープンキャンパスで、現役の学生に「なぜその大学を選んだのか」、「入学して何を学んだのか」といった疑問に思ったことを解消するといい。
感想
アットランダムに感想を述べさせていただきます。
関西で“チャレンジ校”といえば、近畿大学ですね。その象徴はやはり“養殖マグロ”といっても失礼にあたらないでしょう。
常見氏は「自分が興味を持った大学の、実際の講義に潜るのもいい」と述べておられます。覆面学生ですね。素顔の大学、素顔の学生から、真に有益な情報を得ることは大切なことです。
オープンキャンパスを全否定するものではありませんが、そこで得られる情報は、どうしても「大学からの売り込み情報」になりがちです。
高校の段階で、将来やりたいことや進路を見つけるのはむずかしいかもしれません。大学を出たあとも何をしていいか分からない若者もいるくらいですから(その気持ちはよくわかります)、むずかしいところです。
学部教育では汎用性能力を養う教育でいいのではないか、という思いもあります。リベラルアーツの意義はそこにもあるのではないでしょうか。
受験生が「偏差値なんて信用できない」と思っているわけですから、そうなると偏差値に一喜一憂しているのは、大学や高校それに予備校等ということになります。偏差値偏重の考え方を変えねばならないのはこれらの機関ということになります。
The following two tabs change content below.

大学職員ブロガーです。テーマは「大学職員のインプットとアウトプット」です。【経歴】 大学卒業後、関西にある私立大学へ奉職し、41年間勤めました。 退職後も、大学職員の自己啓発や勉強のお手伝いをし、未来に希望のもてる大学職員を増やすことができればいいなと考えています。【趣味】読書・音楽(主にジャズとクラシック)・旅 【信条】 健康第一であと10年!
最新記事 by 瀬田 博 (全て見る)
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(3) - 2018年12月25日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(2) - 2018年12月20日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(1) - 2018年12月19日