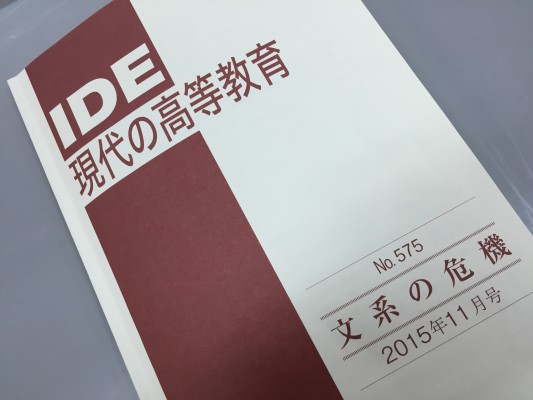音楽は毎月1,000円払えば聴き放題
Apple Musicが日本でもリリースされました、3ヶ月間の無料トライアル中の方も多いことでしょう。プレイリストがうまく同期できないというトラブルもあったようですが、これはイケるサービスです。
iPhoneの場合はiOSを、PCの場合はiTunesをそれぞれバージョンアップすれば使うことができます。ちなみに、ラジオステーションのBeats1は無料で聴くことができます。
自分で使ってみた経験からの結論ですが、もうこれからはCDを買うことも少なくなるだろうなという予感です。世界一のCD(パッケージ)王国であるわが国も、いずれ大半がストリーミングサービスに移行するのではないでしょうか。
CDを買ってもiTunesに取り込みますし、スピーカーに向かって聴くこともずいぶん少なくなりましたから、考えてみればこれまでとあまり違和感がないのですね。
次は電子書籍?
イケダハヤト氏が「[予言]『音楽ストリーミング』が話題だけど、『電子書籍』も読み放題が当たり前になるよ」と述べています。毎月1,000円払えば読み放題というわけです。
すでに国内でも、
- ソフトバンク
- au
- 角川文庫プレミアムクラブ(500円で文庫が読み放題)
- Comic Walker
がサービスを開始しており、
米国Amazonでは、月額9.99ドルの読み放題サービス
をすでにリリース中です。
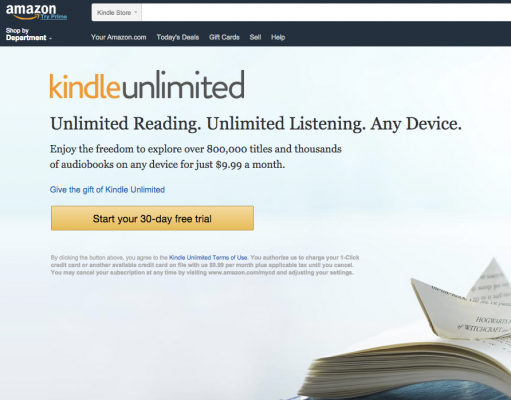
出版社・著者のビジネスモデルも変わる
イケダ氏は以下の予測をしています。
- 定額制になると、「閲覧数・ダウンロード数に応じた収益分配」となる。
- あえて定額読み放題に参加せず、単品販売する著者も登場する。
- 出版社・編集者は、著者を全方位的にプロデュースする、芸能プロダクションのような機能が強化される。「いい本を出す」のは前提で、そこから先のつながりをデザインすることが求められる。
- 将来は、「本は買うもの」ではなく、「本は契約して読むもの」になる。
定額読み放題が大学に与える影響
近畿大学・アマゾンジャパンの連携協定が話題になりましたが、定額読み放題が当たり前になれば、教科書の販売方法も変わってくる可能性があります。
シラバスやそのほかの大学の印刷物も、これまでのPDF形式ではなく、電子書籍で提供できるとなると印刷経費がかからないことになります。
そう考えれば、
- 学生の経済的負担が少なくなる。
- 大学側も印刷経費が軽減される。
というメリットがあり、これは学生・大学ともに歓迎すべきサービスということになります。
課題は、教科書や参考文献がどれだけ電子書籍化されるかということです。米国では、管見の限りではありますが、多くの書籍が電子書籍化されているようです。
日本では電子書籍とそのリーダー・デバイスの普及は、まだ過渡期の段階ですので何とも言えない状況ではあります。
ともあれ、いま、私たちの想像を超えたコンテンツ販売の革命が進んでいることは間違いないようです。
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(3) - 2018年12月25日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(2) - 2018年12月20日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(1) - 2018年12月19日