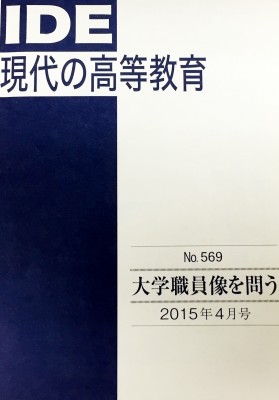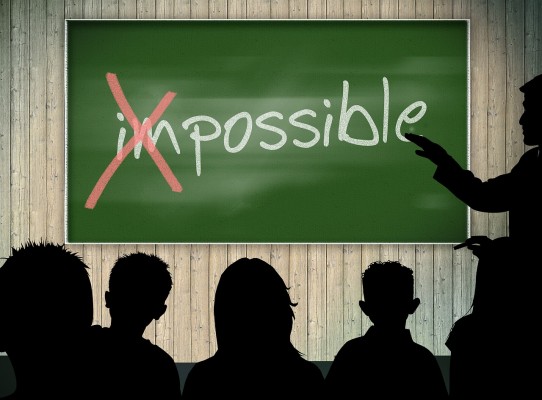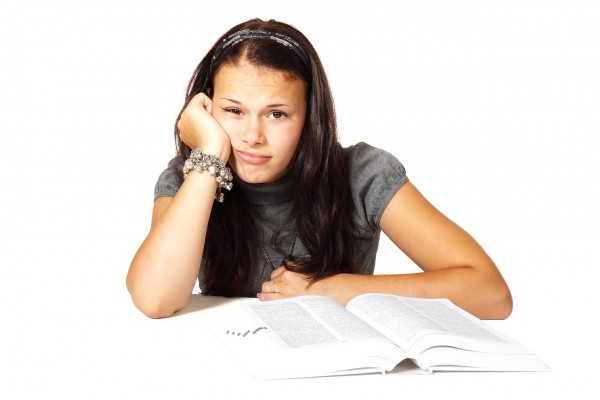「大学職員に期待すること〜公立大学の学長から」奥野武俊(前大阪府立大学 理事長・学長/海洋システム工学)
要約
- 大学の経営・管理だけでなく、教学についても積極的に関与すべきことが期待され、日本における大学職員に関する議論は新たな段階に達している。
- 従来の大学職員とは異なる”専門職”を特別な職種として設ける議論も行われている。
1.地方公務員としての公立大学職員
- 設置者(法人化された後では設立団体と呼ばれる)から、自治体職員が大学に送られてくる。
- 数年毎の異動サイクルによって自治体本部に戻ったり、他の出先機関の職員として勤務するのが普通
- 当然のことながら設立団体との話し合い業務は多く、税金で運営している「公(おおやけ)」という立場に対する理解とスキルは必須であり、これができた上で従来の発想を超える柔軟性が求められている。
2.大学特有の業務
- 委員会運営そのものに対する思い切った見直しと、なによりも教員の意識改革が必要
- 大学職員には高度な知識やスキルが必要となるが、大学はその実現を促す環境を作らなければならない。
- 教員が昔のままの方法で、職員を”事務補助”のように考えるやり方では、これからの時代を乗り切っては行けない。
- 教員も職員も危機感を持って、大学職員と教員のフラットな組織を作って業務を進める方法を模索する必要
- 大学職員に専門的な知識やマネジメント力が求められることになり、これは大学職員のプロフェッショナル化と呼ばれる問題
3.大学職員組織などにおける課題
- 企画力の資質が高く、将来は教員と対等に仕事のできる職員を育てるつもりで採用しても、彼らの上司が、たとえ優秀な公務員であったとしても、これからの大学に必要なことや将来に対するビジョンを共有していなければ、若い職員を育てることは難しい。
4.大学職員に期待すること
- 職員個人が新しいことを学ぶこと以上に、自分の個性を生かすヒントに”気づく”こと
- 大学職員自ら専門的な知識やスキルを高める意欲を持つことが何よりも大切
5.おわりに
- 成長した意識の高い大学職員を生かすためには、活躍できる環境を整えなければならない。
感想:活躍できる環境を
数年ごとに異動があり、自治体本部に戻ったり他の出先機関へ行くのでは、所属する大学に愛着を持つことは難しいように思います。前回に見た国立大学法人の変貌ぶりとは対照的な記述なのですが、実状はどうなのでしょうか。
繰り返し主張されていることは、能力も意識の高さも兼ね備えた職員が活躍できる環境の必要性です。3.の上司の問題もその一例です。
「勉強だけではダメ」と言われないように、理論と実践を両方勉強できる環境整備は本当に大事です。大学院で学んだ職員の処遇についても、明るい話題はあまり聞きませんが、周知のようにこれは企業でも同様のようです。高等教育機関でこそ、このことについて先鞭を付けるべきだと考えます。
The following two tabs change content below.

大学職員ブロガーです。テーマは「大学職員のインプットとアウトプット」です。【経歴】 大学卒業後、関西にある私立大学へ奉職し、41年間勤めました。 退職後も、大学職員の自己啓発や勉強のお手伝いをし、未来に希望のもてる大学職員を増やすことができればいいなと考えています。【趣味】読書・音楽(主にジャズとクラシック)・旅 【信条】 健康第一であと10年!
最新記事 by 瀬田 博 (全て見る)
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(3) - 2018年12月25日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(2) - 2018年12月20日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(1) - 2018年12月19日