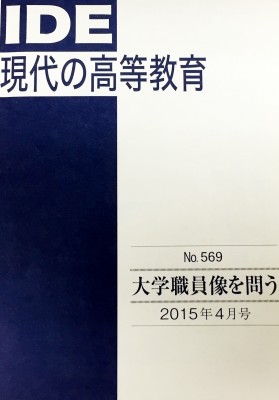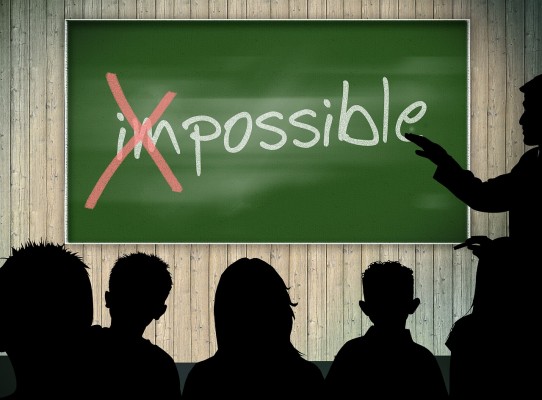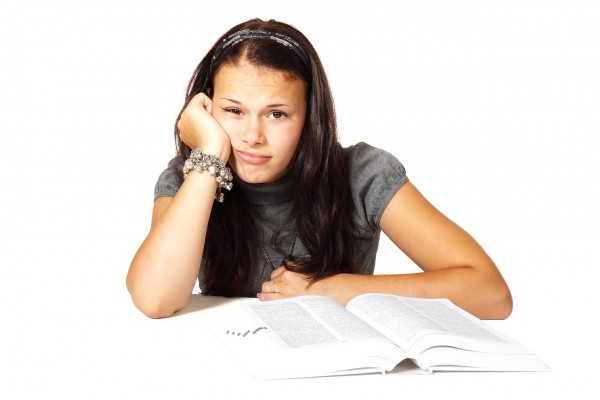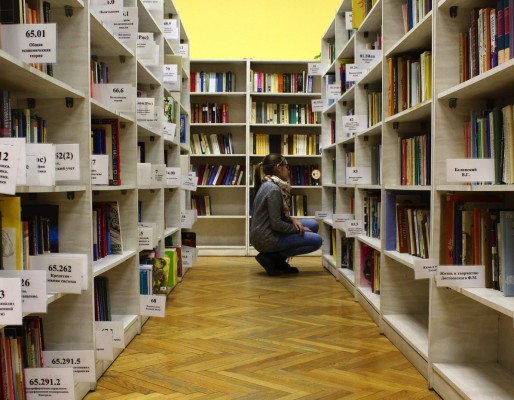「『事務』職員から『大学』職員へ」第12回目です。
この記事は、福島一政氏の第1回高等教育推進センターSD講演会(関西学院大学)での講演をご紹介するものです。
出典:関西学院大学高等教育研究第2号(2012年3月)
今回は、「SDの目的と進めるにあたっての自律性と組織性」です。
SDの目的と進めるにあたっての自律性と組織性
SDの目的
まずSDの目的です。
福島氏は、
- 「大学改革実現へのマネジメント業務のできる職員の能力開発」
(大学行政管理学会のSDプログラム検討委員会)
を紹介したあと、以下のようにご自身の定義を述べています。
- 大学が、複雑多岐にわたる課題を自律的に解決し、社会的な存在として発展していくためには、大学経営や運営で、職員の能力向上が必須
- 単なる研修の積み重ねではない
- 職員への権限移譲が不可欠
これらを裏返すと、現状(過去)の職員は、
- 課題を自律的に解決していない。
- 研修をSDと考えている。
- 権限移譲されていない。
となります。
厳しい条件ではありますが、いよいよ「職員の出番」が来たわけですから喜ぶべきことだと思います。
SDを進めるにあたっての自律性と組織性
こう指摘されています。
- 職員集団が自律的にSDプログラムを検討する。
- 自らの組織と個人の成長は自らの手で決定する。
- 依存的な体質を改め、大学経営と運営における責任意識をつくっていく必要がある。
「自律性」が強調されています。
外部のリソースを使うのはいいけれども、しかしプログラム自体は職員自らが検討しなければならないと私も考えます。
「自らの組織と個人の成長は自らの手で決定する」。当然のこととはいえ、心すべきすばらしい言葉です。
SDという言葉
「なぜ大学にSDという言葉があるのだろうか」、「ほかの業界にこのたぐいの言葉はないよ」。
こんな指摘をよく聞きます。
教員にはFD、職員にはSD、とセットになっているのがおそらくその理由だと私は単純に解釈しています。 しかし言葉の詮索などより、職員の能力向上が必須の時代となったことが重要なのです。
上記の3点を脳裏に刻み、組織的に精進していかねばなりません。
⇒第13回:SDで何を変えるか 「事務」職員から「大学」職員へ(13)を読む。
【目次】「事務」職員から「大学」職員へ 福島一政氏の講演から
The following two tabs change content below.

大学職員ブロガーです。テーマは「大学職員のインプットとアウトプット」です。【経歴】 大学卒業後、関西にある私立大学へ奉職し、41年間勤めました。 退職後も、大学職員の自己啓発や勉強のお手伝いをし、未来に希望のもてる大学職員を増やすことができればいいなと考えています。【趣味】読書・音楽(主にジャズとクラシック)・旅 【信条】 健康第一であと10年!
最新記事 by 瀬田 博 (全て見る)
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(3) - 2018年12月25日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(2) - 2018年12月20日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(1) - 2018年12月19日