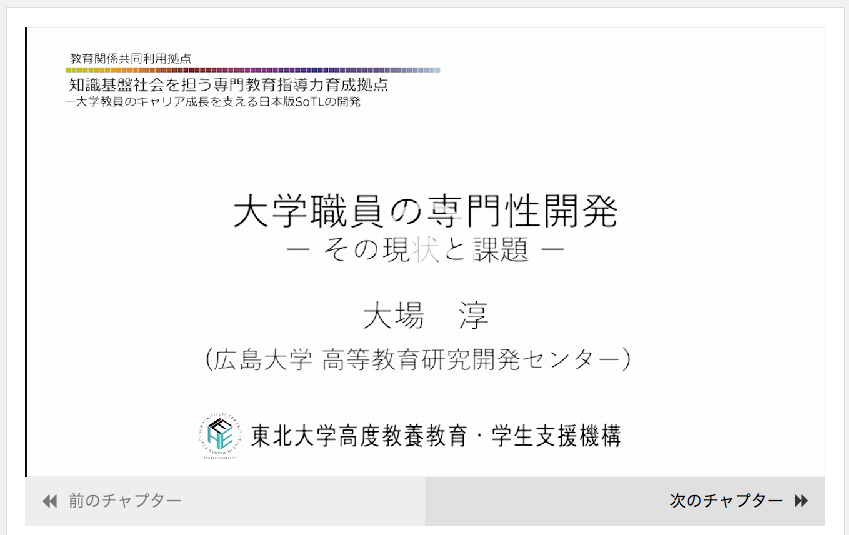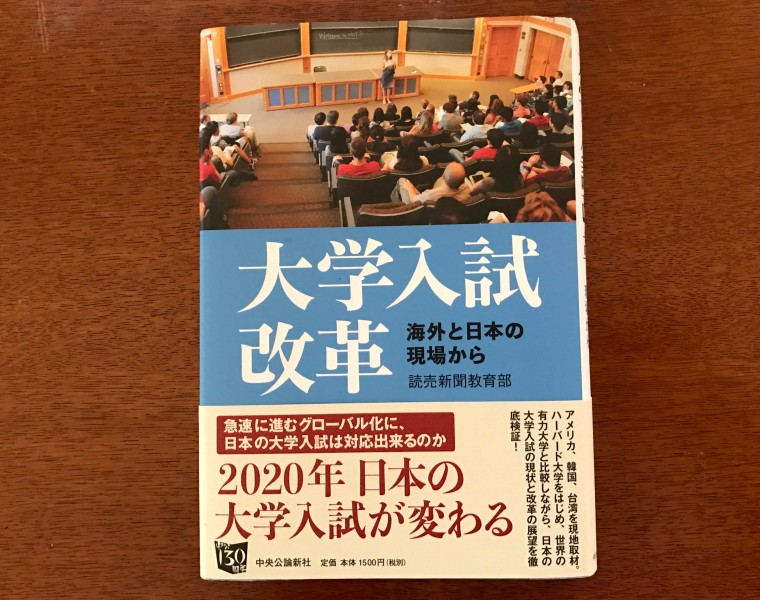このページの目次
はじめに
東北大学高度教養教育・学生支援機構のPDP(専門性開発プログラム:Professional Development Program)サイトからの講義のご紹介である。
これは、大場 淳氏(広島大学高等教育研究開発センター)が、関係共同利用拠点提供プログラム「大学人材開発論」として、平成28年4月29日に東北大学で行った講義の動画である。
大学職員として、どのような専門性を身につければいいのか悩んでおられる若い職員の人たち。
専門性育成のために、今後どのような取り組みをしなければならないのかと頭を悩ましておられるマネジメント層の人たち。
この講義は、そういった人たちに、有益なヒントを与えてくれる。
どうぞご覧いただきたい。
筆者が重要だと感じたことを、以下ご紹介しよう。

大学職員の専門性開発ーその現状と課題ー
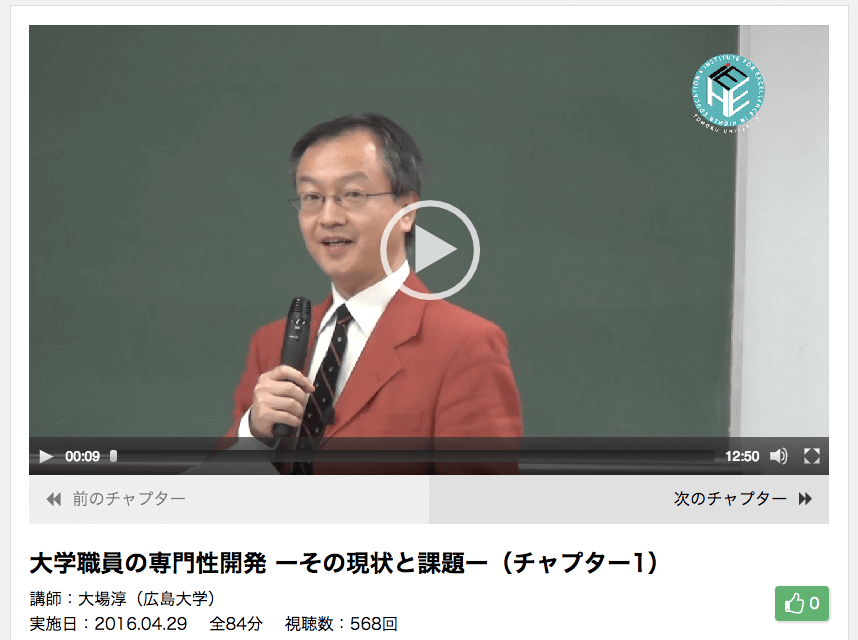
目次
- 大学職員の現状
- 専門職に関するこれまでの検討
- 最近の政府における議論と政策
- 米国との比較
- 大学職員の専門性を巡る諸論点
- まとめ
米国における専門性を支える様々な仕組み
つぎの項目が挙げられている。
- 労働市場、高い流動性
- 専門性養成、流動性促進の場としての専門職団体
- それに適した人事制度(CDP)に基づく職員評価・養成(支援)
- 職員向けの大学院教育(高等教育研究の修士課程プログラム)
これらのことは、日本ではまだ不可能なので、「一定の時点で特定の分野でのキャリアを進むことを可能にすること」が現実的である、と大場氏は述べておられる。
“第3の領域”ー日本における境界不明瞭化の議論
天野郁夫氏と孫福 弘氏のつぎの発言が引用されている。
アメリカの大学では以前から進行していることですが、日本の大学でも教員と職員の境界があいまいになっていくというか、境界的な仕事が増えつつあります。…高い専門性をもった新しいタイプの職員を育成していかなければ、教員の仕事は増えるばかりでしょう。(天野,2001)
行政管理職がこれまでしばしば教員の兼務職位として片手間に遂行されてきた弊害を指摘してきたが、これも大学構成員の種別が「教員」「職員」の二分法で律しられてきたところに原因の一つがあるのではないか。その意味で、第三の自律的カテゴリーとしての「行政管理職員」の確立は、高度のプロフェッショナル職位の認知をより明確にし、大学運営の成熟に大きく貢献するものと思われる。(孫福,1996)
この“第3の領域”こそがー孫福氏も指摘されているようにー大学運営に大きく貢献するものであろう。
そして、専門的職員への関心が強くなったことも、このことが大きな要因ではなかろうか。
この領域への進出は、教員も歓迎するのではないか。多忙をきわめる教員の業務をすこしでも軽減することは、喫緊の課題であるからである。
単なる“雑務”ーこの軽減も重要な課題だがーではない高度な業務であればなおさら歓迎されるばかりではなく、むしろ、これまで望まれていたことではあるまいか。
そう考えるのである。
せめてこれぐらいは積極的に推進すべきこと
大学分科会「大学のガバナンス改革の推進について」(審議まとめ)から、以下のような項目が紹介されている。
- 企画力・コミュニケーション力・語学力の向上
- 人事評価に応じた処遇
- キャリアパスの構築等についてより組織的・計画的に実行していくこと
- 国内外の他大学、大学団体、行政機関、独立行政法人、企業等での勤務経験を通じて幅広い視野を育成すること
- 社会人学生として大学院等で専門性を向上させること
これらを積極的に推進すべきである、としている。
筆者としては、先進的なNPOでの勤務体験もつけ加えたいところだが、それはともかく、この程度のことでも、本格的に推進している大学は少ないのではないか。
制度整備に当たっての実践上の論点
制度整備に当たっては、それぞれの大学によって事情が異なることから、以下の項目について考えることが必要である。
求められる専門性は何か
- 専門性が必要とされる領域
- 大学運営に必要な専門性(優先付)
養成と資格
- どこで養成するか
(OJTや学内研修、行政組織や民間組織、大学間団体、専門職団体)
- 大学養成課程の整備と活用
- 資格は必要か、どのような資格を設定するか
ー処遇とキャリアパス
- 雇用形態、給与体系、評価制度
- 魅力あるキャリアパスの提示
- 異動を容易にする仕組み(労働市場、年金等)
ー外部人材の登用の在り方
まとめ
大学職員の専門的機能の確保は避け難いが、同時に専門職化は容易ではないと指摘されている。
容易ではないことの理由として、
- 専門職のキャリアや職能開発
- 多様な必要性:大学によって異なる需要
- 第三領域、専門職員のアイデンティティや教員との関係の在り方の見直し
- 経費の問題
が挙げられている。
では、どうすればよいか?
このことについては、
ガバナンス改革(研究)の中で、職員の専門性向上を併せて検討すべきであり、個人ではなく組織に着目した取組の必要性
と指摘しておられる。
これが本講の結論といえようか。
職員の専門性開発への大きな障壁が、わが国の雇用形態と人事制度にあることは確かである。
ジョブ型採用に転換しなければ、専門的職員をめざす人材は増えることはないであろう。
現状では、任期制職員や非正規職員になる可能性が高いからである。
したがって、上記で指摘されているように、「一定の時点で特定の分野でのキャリアを進むことを可能にすること」が現実的な道なのかもしれない。
ともあれ、これからの大学職員は「ゼネラリスト+キラリと光る専門性」といった生易しいものではなく、本格的な専門性を身につけなければならない時代だといえよう。
とくに“第三の領域”に属する専門性を身につけた大学職員は、来たるべき人材流動の時代にはひっぱりだこになる可能性が高い。
チャレンジする価値は十二分にある。
最後になったが、この動画について要望を出しておきたい。
- 分割されているので、通しで再生できない。
- テキストがダウンロードできない。
すばらしい内容なので、このような注文をすることは気が引けるのだが、思いきって述べさせていただいた。
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(3) - 2018年12月25日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(2) - 2018年12月20日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(1) - 2018年12月19日