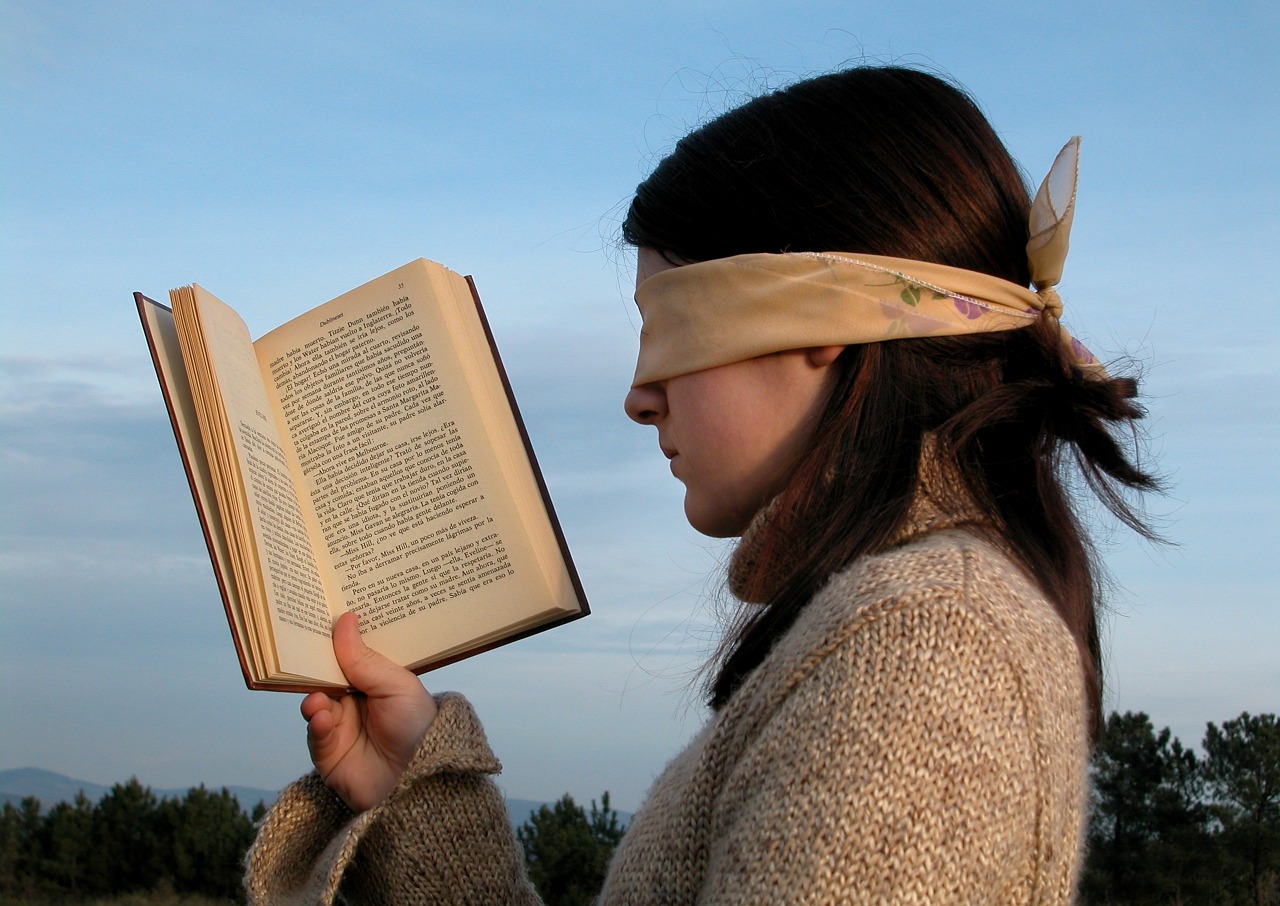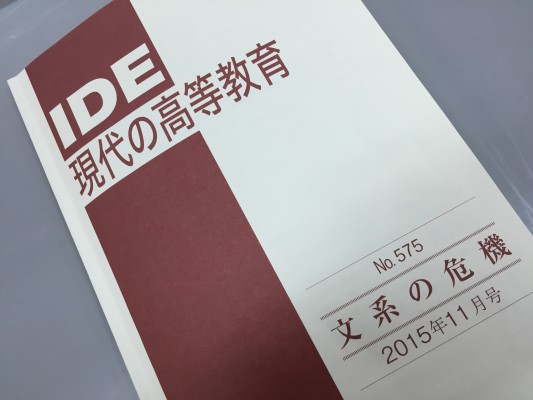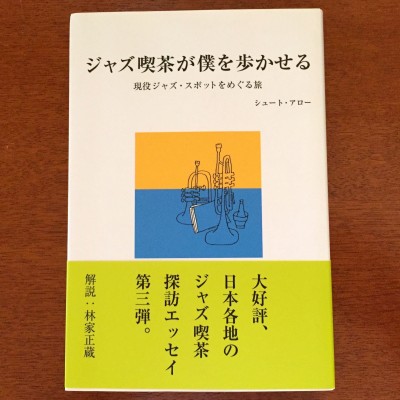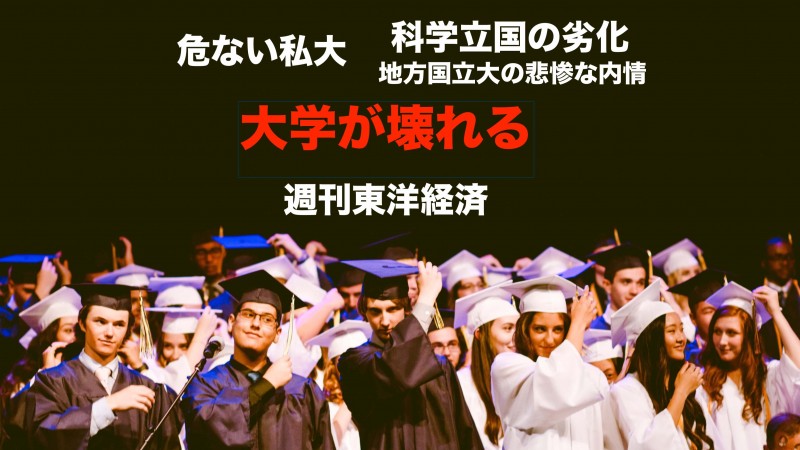本書は野口悠紀雄氏自身が音声入力で書いた著作である。
iPhone→iPod→PCのテキストエディタ→紙(プリントアウト)→出版という流れだそうだが、iPhoneを使って音声入力を行っている。
それではご紹介しよう。
このページの目次
野口悠紀雄氏が述べる本書の目的
将来発展すると考えられる技術が現われたら、それに対応して、仕事のやり方や生活のスタイルを変えることが必要。
音声入力は間違いなくそのような技術。
「本書で論じたいのはこのこと」と述べている。
音声入力は画期的な技術革新
音声入力の仕組み
音声認識機能がスマートフォンの中に収納されているわけではない。
入力された音声は、インターネットを通じてアップルやGoogleのコンピュータにつながり、そこで解析された文字のテキストに変換され、それが自分の画面に表示される。
音声入力が今後ますます進歩する技術であることは間違いない。
アナログ・ディジタル変換の真打ち技術
人工知能とは、自動学習能力を持つコンピュータである。
ディープ・ラーニングまたは「ニューラルネットワーク(神経系ネットワーク)」と呼ばれる機械学習の手法。
iPhoneの音声認識機能であるSiriは、もともとは米国防総省のプロジェクトとして開発されたもの。
人間が最も自然な方法で機械に入力できるようになったという意味で、音声入力は、人類史上における画期的な技術革新。
音声入力のメリット
3点紹介されている。
- PC(パソコン)のキーボードで入力するのに比べて、約10倍の早さで文章を書くことができる。
- プレゼンテーション能力を鍛えるために、大変重要な意味を持つ。
- 検索を音声で行なうことができるようになったため、知りたいことが生じたとき、その場で直ちに情報を得ることができるようになった。
高齢者がリープフロッグ(蛙跳び)できるツール
最初から新しい技術を使う新しい世代に追い抜かれることを、「リープフロッグ(蛙跳び)」という。
スマホのフリック入力派は音声派に追い抜かれていくことになる。
高齢者などこれまでIT機器をあまり使っていなかった人々が「追い抜く」ほうに含まれうるのが特徴。
スマホは高齢者にとって最適の端末となる。
仕事の仕組みや進め方が大きく変わる
以下の事柄について詳細な解説が述べられている。
●メモ
●メール
- 現在電話で行われている仕事上の連絡の多くがメールになる。
- 組織内のコミュニケーション、共同作業者との間のグループ内コミュニケーションの形態は大きく変化する。このような変化に対応できる組織が、真のグローバル組織になる。
●アイデア
- 音声入力によって容易に文字にすることができる。
- アイデアを成長させることができる。
●「見える化」
●いつでもどこでも検索
- キーワード検索からセマンティック検索への移行は、検索における重要な変化
●スケジューリング
まとめ
野口氏は最後に、
重要なのは、いまや「文字を正確に話す」ことと、「文章の構造を正確に作ること」
と述べている。
また、音声入力の最も有効な使い途は長文のテキスト化とも述べている。
現在のところ、音声入力が与える影響について、声高な意見を聞くことは少ないように思われる。
だが、野口氏も指摘するように、将来ますます発展することが確実な音声入力は、今後ビジネスやライフスタイルを変えることになるのかもしれない。
そのときになって、野口氏の先見の明に驚くことになるのだろう。
本書を読んで、音声入力を試してみたいと思う人は多いであろう。筆者もその一人である。
多くの方にオススメできる良書である。

- 作者:野口 悠紀雄
- 出版社:講談社
- 発売日: 2016-05-20
本書で推奨されているアプリはこちら
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(3) - 2018年12月25日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(2) - 2018年12月20日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(1) - 2018年12月19日