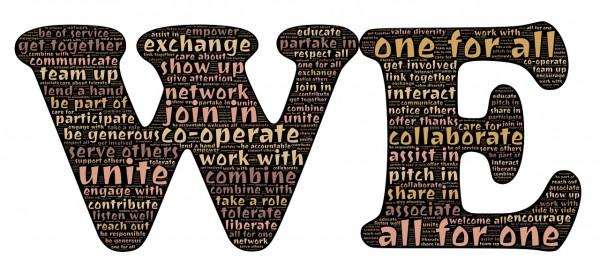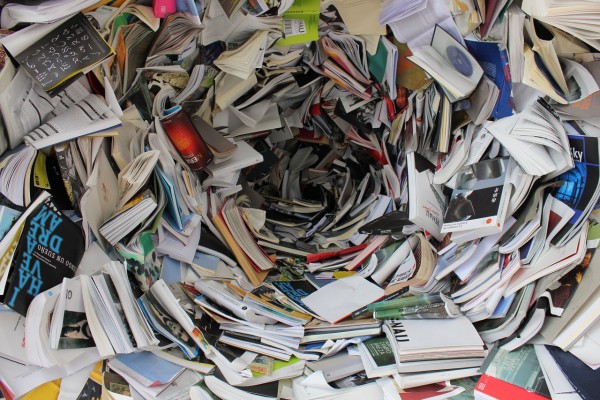このページの目次
はじめに
現在多くの大学で導入されている担任制。
制度が形骸化している大学もあるようですが、一方で、「教育学術新聞」には機能している大学の事例が紹介されています。
担任制が機能している大学の事例
群馬医療福祉大学
- 学生の出席状況を把握。
- 月1回の教授会と教員会議に報告。
- クラス担任から学生に個別指導。
びわこ学院大学
- クラス・ゼミ担任制で導入。
- 進路指導・自己分析もサポート。
足利工業大学
- 2年次以上では、複数の教員を担任に配置。
美作大学
- 職員が学生情報を管理し、問題がある学生は担任と情報を共有して支援。
弘前学院大学
- 2週連続で休むと要注意情報を共有、3週続くと本人面談。
- 必要に応じ保護者と協議というカウンセリング・支援体制。
中央学院大学
- ゼミでクラス担任と学年担任制のダブル担任制。
千葉工業大学
- クラス担当教員のほか、約10名程度の学生グループに1人ずつメンター(教員)がサポート。
- 第2メンターや事務職員もサポートに。
- 1人の学生に4人以上の教職員がサポート。
平安女学院大学
- 上級生がチューターとなり、学生評価シートを作成・活用。
- 就職の個別相談では、教職員がチームを組み、キャリアサポートセンターだけでなく、連携・協力し、学生に合った支援を行う。
美作大学の事例に見られるように、教職員の連携こそが最大の学生支援となる。
また、千葉工業大学のように、教職員が連携して支援していく仕組みは、ムリ・ムダがなく手厚い学生指導となる。
これこそが教職協働の真価が試される場面、と同紙は述べています。
担任力
日本中退予防研究所の山本繁所長のコメントが紹介されています。
- 担任とは「その学生のすべてに責任を持った立場の人」
- 担任力が必要
①学生を把握する力
②学生が抱える課題を解決する力
③クラスを作る力(学生同士の問題解決を促進する力)
- 職員による教員への情報提供(IR)は大事な業務の一つ
①学科単位での経年変化といったマクロな情報
②リアルタイムな学生情報
まとめ
筆者の気づきは以下の3点です。
- 教職員の連携が最大の学生指導となり、教職協働の真価が試される場面
- 担任力を付ける必要
- 職員による教員への情報提供が大事
The following two tabs change content below.

大学職員ブロガーです。テーマは「大学職員のインプットとアウトプット」です。【経歴】 大学卒業後、関西にある私立大学へ奉職し、41年間勤めました。 退職後も、大学職員の自己啓発や勉強のお手伝いをし、未来に希望のもてる大学職員を増やすことができればいいなと考えています。【趣味】読書・音楽(主にジャズとクラシック)・旅 【信条】 健康第一であと10年!
最新記事 by 瀬田 博 (全て見る)
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(3) - 2018年12月25日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(2) - 2018年12月20日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(1) - 2018年12月19日