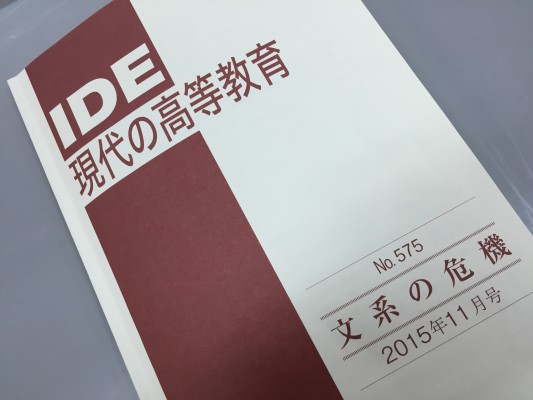ICU、APU、AIU・・・大学関係者しか分からない略語ですが、今回はAIUの話題です。
「IKUEI NEWS」Vol.71(電通育英会)に掲載されている鈴木典比古氏のインタビューです。
このページの目次
要約
教育は“人工植林型”から“雑木林型”へ
- 21世紀に入り、世界の高等教育の流れは教養教育重視へ向かっている。
- アメリカにおける高等教育の方向性を定めたグレイター・エクスペクテーションズ(大いなる期待)という報告書で強調されていたのが「リベラル・エデュケ―ション」、すなわちリベラルアーツ(教養教育)的な考え方が21世紀の教育の潮流になるというものだった。
- 20世紀までの教育は“人工植林型”。同じ考え方の者が集まり、同じような教育を受け、同じような人材の作り出す。これは20世紀までの産業社会が必要とする人材にはマッチしていた。
- しかし、多様な人材が必要とされる21世紀においては“雑木林型”の教育が必要。多様性のある教育。それが教養教育。
- 日本の大学は、かつての専門学部制から、教養教育へと少しずつ移行している。しかし、すべての大学を教養教育系の大学にする必要はない。
- アメリカでは総合大学と教養教育系の大学の共存ができている。
- アメリカには教養教育系の大学が600ほどあるが、小規模で、大学での4年間は専門化せずに学部教育に集中している。卒業した学生は大学院に行き、初めて専門の学問を学ぶ。
- 日本の大学教育の95%以上は専門教育で、教養教育系の大学は数えるほどしかない。教養教育系の大学が増えてくれば、両者の共存は可能で、棲み分けも可能。

英語授業と海外留学が育てる真の国際人
- 本学の教育の特徴は、「教養教育+英語教育+海外留学」
- 「一人として同じ人間は育てない」という教育
- 基本的に3年生になったら一度全員を海外に送り出す。
- 4年で卒業できる学生は半分適度。最大の理由は、海外留学1年間で最大30単位の取得を目指しているため
- 海外留学は語学の研修ではなく、海外で正規の授業を受けて、一定の単位取得を目指す。
秋田発、世界水準のリベラルアーツ教育
- これから取り組むべきことは、リベラルアーツを掲げる世界の大学と協力しながら、日本の高等教育のリベラルアーツ化を推進すること
- その手段の一つが授業の国際交流
- 本学の授業を海外へ発信、海外の授業を日本で受講。授業配信をするための協議を進めている。
- ニューヨーク州立大学の科目の互換をするためのプログラム、COILに参加すること
- 秋田県に対する地域貢献は、「国際教養大学の存在価値を通じて、世界に“秋田”の存在を知らしめること」
常に先進の「国際教養大学」であるために
- この大学が珍しがられてモデルとなるほど、世界と比べ、日本の教育には課題が多いということ
- 世界の大学と比べ遜色のない、世界標準まで引き上げることが本学の課題
- 卒業生のネットワーク作り。留学生を含めた卒業生のネットワークを海外にも広げていきたい。
- シラバスのレベルを上げる。レベルを上げれば、より質の高い大学と互換性を持たせることができる。
感想
「アメリカでは総合大学と教養教育系の大学の共存ができており、日本でも教養教育系の大学が増えてくれば、両者の共存は可能で、棲み分けも可能」というのは新鮮な視点でした。
アメリカでは、コミュニティ・カレッジがリベラルアーツと成人教育の多くを引き受けているそうですが、日本でも小・中規模大学をコミュニティ・カレッジ化するというプランは現実的ではないのでしょうか。
The following two tabs change content below.

大学職員ブロガーです。テーマは「大学職員のインプットとアウトプット」です。【経歴】 大学卒業後、関西にある私立大学へ奉職し、41年間勤めました。 退職後も、大学職員の自己啓発や勉強のお手伝いをし、未来に希望のもてる大学職員を増やすことができればいいなと考えています。【趣味】読書・音楽(主にジャズとクラシック)・旅 【信条】 健康第一であと10年!
最新記事 by 瀬田 博 (全て見る)
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(3) - 2018年12月25日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(2) - 2018年12月20日
- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(1) - 2018年12月19日